存外ファムファタールものは戯曲性が高いから、創作ではよく愛されてきた。
運命の女に翻弄される男の物語。まずモチーフとして魅力的なヒロインが生まれる、そんな女に振り回される男の人生はそれだけで波乱に満ちたストーリープロットになる。つまり物凄く感情的で明快な物語の類だが、その分虚構性が強い。そんな手軽に美味しい物語の類を佐藤亜紀が手に取った、つまり本作は面白いに決まっている素材選択が済んでいるし、圧倒的に読みやすい。
佐藤亜紀が書いた大団円、未知の楽園
引き取られた稚児と双子の姉弟との幼少期は、予備知識なくても誰もが楽しめる。
序盤から広がる牧歌的な世界観は十八世紀のベルギーはフランドルという地方にもよるかもしれないし、この時代の商人の家庭を舞台にしているからかもしれない。商家から市長等の特権階級的な知と世俗や、そこから離れた女性の世界である実在したぺギン会という女性の寄り合いの選択も効いている。
佐藤亜紀的な歴史の重さも、人知を翻弄する勝手な暴力による暗さも皮肉も登場しない。読み進めづらい要素が何もなくするする読める。なぜこんな異質な変わり種を書いたのか、普段の佐藤亜紀作品に慣れた読者はその疑問を持ちながら読み進めるのだと思う。それくらい本作はちょっと変わっている。
振り回す運命の女、奔放な娘の喜びと幸福
三人の幼少期から始まる読みやすさ、双子の姉弟、頭の良い姉ヤケネ、気が良い弟テオ、貰われてくる等身大の男の子ヤン。お前の父は勇敢だった良い男だったと言って仕事仲間の子供を引き取ってくれる家長ファン・デール氏、働き者で理知的だが温かい奥様ファン・デール夫人。卑猥な近所の男の子たち、発達していく身体に自然な興味と快楽による妊娠、後ろ暗さと罪の意識、引き受ける母体と隠れて心に誓う男の責任感。隔離と出産、開けていく世界と計画的な書庫、名を偽った博士論文の執筆、親の危篤。
こと一般的な運命の女は大抵の場合、若く艶やかで美貌と色気に満ちた姿形をしている。本作の女は出会いの年端こそ少女だったが、外見はほとんど触れられずに幼少期から際立って表現される賢さは、商家に生まれたのが勿体ない、女に生まれたのが勿体ない、と並ぶ。相手の男を隠して子供を産み、世に落とした子を一切育てずに女だけの奥地に引っ込む、弟の代筆で博士号をとろう、本を出版しようと画策する、深遠な知性が畑仕事をする、外に残された男は家業をさせられる。
振り回される運命の男、男女に生まれた形の定め
床に腹這っていたヤケネを思い出してヤンは声を殺して笑う。床にべったり腹這ったぺギン。よくやったぞ、レオ。真っ黒い服を着て白い布被って、人類が未来永劫行き着けない場所にある星の見掛け上精確な位置を割り出すくらいにしか使えない方法を考え付いた半分尼さんを、着るものがどうなろうとお構いなしに床に腹這わせるのはお前くらいのもんだよ。どうだい、お前の母さんは。いやいやするか。あんなの母さんじゃない、ってか。ばあたんもじいたんもとうしゃんもいるから、母さんなんかいらない、ってか。いい度胸だ。一生教えてやる気はないが、それでもお前、自慢にしていいぞ。立派なもんだ。
~~~~~~~
「上り調子すぎる。いいことなんだけど、だからテオが死んで色々厄介なことになった、というのが、カタリーナから色々聞いて思ったこと。兎も角いい話が来てるんだ、願ってもない、ってやつ。ヘントの糸問屋の跡取り息子とか心当たり、ない? いっぺん断ったのにまだ言ってくるって。クヌーデの娘ってだけじゃない、彼女を射止めると、横から上り調子の商売を丸ごと手に入れられるからね」
「いいよ、持ってけよ。おれは仲買でも何でもするから」
「まだそんなこと言ってる。これだけばりばりやっといて、今更仲買とか、何が起こったんだろう、って話になるよ。それにカタリーナが再婚して息子が生まれたら、父親はその息子に全部譲りたいと考えるだろうね。そうしたらルイはどうなるの。クヌードのおやっさんだって、づなればそれはそれでいいと思うかもね。孫はおんなじだしも元々うちが嫌いだもの」
「俺がいるだろ」
「あんたはルイの父親じゃない。伯父ですらない。今はね」
なあ、とヤンは言う。「俺、金貯めてるんだ。家買って出直せるくらいの金だ。仲買はやめろと言うんなら、それで別の商売を始めるよ。伝はある。アムステルダムともパリとも繋がりは作った。ルイもレオも引き取れる。お義父さんも引き取る。だから出てきて一緒になってくれないか」
言っちゃったか、とヤケネは言う。「無理。今忙しい」
「他の女なんかいらないんだよ」
ヤケネはヤンの肩を軽く叩く。家族の肩を叩くような叩き方だ。その手を捕まえようと思うが、捕まえられない。「ルイの父親になってやる、って考えて、何が一番いいか考えて。どうしてもいやだというなら、あたしも一度全部ばらして組み直すところから考えるけど、でも答えは同じだと思う。多分あんたもだよ。よく考えて」そのまま、家に入ってしまう。追いかけようにも足が動かない。木戸の先は立ち入り禁止だ。
ヤンはレオを連れて広場に出る。レオが小走りにならなければついていけない勢いだ。呼んでも答えない。運河のそばに出て店の前に差し掛かる。ルイが中から窓を叩いたのにレオは気が付くが、ヤンは素通りする。どんどん歩いていく。レオもついて行く。市門を出て、運河に沿って歩いて行く。
人でなし、と思う。人でなしの女に人生滅茶苦茶にされる、と思う。あの店はヤケネの店でもある、それを手放したくないってか、と思う。利用されている、と思う。弄んで子供ごと捨てた、お人よしにつけ込んでいいように働かせてる、と思う。身勝手な人でなし、と思う。思いながら、方程式を解くように考えている。こうやって、ああやって、駄目だ、出口がない。一度ばらして考える。もう一回。さらにもう一回。何度も最初から考え直してみる。引っ張ってこられる限りのものを引っ張ってきて組み立て直して考える。繰り返し考える。やっぱり駄目だ、すべての条件を満たす解は他にはない。人でなし。
~~~~~~~~~
カタリーナに求婚した、とぶっきらぼうに投げ出す。「カタリーナは喜んでる。子供たちも喜んでる。ルイには、お前が大人になるまでの後ろ盾だと言った。クヌーデのおっさんも喜んでる。扱いがいいと思われてるんだよ。クヌーデ夫人も喜んでる。娘が喜んでいればそれでいいんだ。お義父さんも喜んでる、多分」俺は喜んでない、と心の中で付け加える。「満足か」
「うん。ありがとう。御免ね」
「六月に結婚する。婚約は知れ渡ってるんで家に戻った」
「その方がいいよ、あんたの家なんだから」とヤケネは言う。
~二人きりになるとカタリーナは涙ぐんだ。テオは優しい人だった、隠し事もしなかったし、夫婦の務めも必要な時はちゃんと果たしてくれた、けれどやはりまともな人ではなかった、と言うのだった。まともな夫が持てて嬉しい、あなたは立派なちゃんとした人だとずっと思っていた、あなたのような人が夫だったどんなにいいだろう――どんなに安心だろうと前から思っていた、と。
縋り付いて泣くカタリーナを慰めた。慰めついでに抱いた。まだ若いし、不器量という訳でもないし、相変わらず栗鼠のような顔は頬が少し痩せて、何より可哀相ではあるので、寝間着を捲り上げるともう準備は万端で、その後のことはつつがなく済ませることが出来た―出来たが、その間もずっと考えていた。
なあ、まともって、何だよ? 全部あの人でなし女のせいだが、それでも唯々諾々とこんなことやってる俺が、まともか?
ヤンはヤケネが父親を明かさずに産んだ男児レオを引き取ってファンデール商会で働き続ける。さらに、一人目の妻が疫病でなくなるまでにコルネリアとピエトロネラという名の二人の娘を産んでもらい、その妻の連れ子である長男ルイと長女テレーズを引き取る。この時点では、母親違い、父親違いの子供の計五人の事実上の父親となっている。
ヤケネとの子であるレオだけは他の家族に馴染めずに近くの小屋で暮らし、三人の娘たちは仲良く自由にベギン会に出入りして、叔母さんでもあるヤケネに勉強を教わったりしながら成長する。ある日、長女であるテレーズは今後の活路と希望についてとヤンに相談する。レオは義理の妹がべギンになると聞いて、髪を掴んで鏡の前で服を剥いて見せつけてその体の役割について暴言を吐く。
ヤンは仕事も姿勢も誠実、引き取ってくれた家長(ヤケネの父)に対して恩があり、次々集まってくる家の仕事と義理の子供たちを請け負っていく。いつまでたっても一緒になってくれないヤケネを思い続けるヤン、そんな父親を持つレオの女性蔑視はかように激しい。この父親に対してこの息子という反転に関して、息子は知性も商売もあんたには敵わない、と父親を尊敬している風は作中一切崩さず、自分は土着的な農園生活のが性に合ってる等と言いながら、自分は何も拡げずに女だけを獲得できる性別に生まれたと思いあがる息子を持つ親は居た堪れない。
あのね、とテレーズは切り出す。「べギンになろうと思うんだけど」
ヤンは軽く溜息を吐く。ヤケネが言っていたからだ――うちの子たちは信仰深いねえ。今時の流行じゃないのかと訊いたが、いや、とヤケネは答えた――テレーズの友達とか見ててもあんなに信仰深いってことはないかな。
「アマリアさんは色々教えてくれる。楽器とか、歌とか、絵の描き方とか、品のいい話し方とか、品のいい立ち方や歩き方とか。髪の結い方や服の着こなしは教わるまでもないよね。私もコルネリアもピエトロネラも見てるだけで上手になっちゃう。ちょっと上手になり過ぎなくらい。晩餐会とか舞踏会の話とかオペラ見に行った話とかも聞いたよ。世間って広いんだなあ、とんでもない世界があるんだなあ、って感じ」
なんともなしにヤンはほっとする。娘たちがアマリアを嫌うのを恐れていたが、そういうことはなさそうだ。
でもね、とテレーズは続ける。「なんかそういうのは違うって感じがした」
「違う、って、どういう風に」
「綺麗なお嬢さん、って言うかな。お義父さんが許してくれるならブリュッセルに連れて行ってくれるし、いろんな人にも紹介してあげる、きっとみんな綺麗なお嬢さんって褒めてくれる、って言うから、有難う、嬉しい、って答えたけど、でも本当は全然ぴんと来なかった。綺麗なお嬢さん、はねえ。それよりレース編んでる方が全然いいよ。最初はヨアンナさんに褒めて貰うと嬉しかったけど、今はもう自分でどのくらいいいかわかる。ほんとこんなちっちゃな」指の先を示す。「モチーフでも、ああこれはいい出来だ、って自分でわかる。嬉しいよ、それは。でも同じくらいうれしいのは、三箇月とか半年とか掛けて作ったレースがちゃんとお金になること。この前初めて、これなら売り物になる、って言われて、ヨアンナさんが売ってくれた。ハンカチのほんと細い縁で、半年掛ったんだけど、お義父さんレースの値段知ってるよね? すごいよ。修道院の寮費が一年分出ちゃう。ヤケネ伯母さんに預けてあるけど、ああ、レース作って、それで自分で生きていけるんだ、って思ったら――何だろう、すごく強くなった、って感じ? その感じはね、きれいなお嬢さん、より全然いいんだよ」
~~~~~~~~~~~
「ペギンになるから家を出るのよ」
お兄ちゃん、やめて、とコルネリアは言ったが、レオはテレーズの髪を掴んで、妹たちの悲鳴の中を廊下まで引き摺り出した。抵抗すると見境なくこぶしで殴り付けた。壁に背中を打ち付け、体を起こした時、レオはテレーズを外出中のアマリアの寝室の衣裳部屋に引き摺り込むところだった。コルネリアは更に追い掛けて、暖炉の火掻き棒を手に取った。
レオはテレーズを衣裳部屋に投げ込むと、兎の皮でも剥くように服を引き裂いてはだけさせ、また髪を掴んで大きい姿見に向き直らせた。見ろ、と叫んだ。
「乳と腹だけだ。お前はそういう生き物だ。子供を産んで育てる容器だ。こんな頭なんかお飾りだ」と言って揺さぶった。テレーズが逃れようとすると左手で顎を掴んだ。「よく見ろや、おまんこ。子供を産むんだよお前は。他の能なんかないだろうが。ごろごろ子供を産み落とす為にいるんだよ。逃げられると思うな。他の事なんかしようとするな」
それから手を離すと吊るしてあったアマリアの衣裳を掴んで、床に蹲って泣きながら震えているテレーズに投げ付け、着ろ、と言った。
「女はこういうのを着るんだ。女らしくして、男に、子供を産ませてくださいと頼むんだ」
騒ぎを聞いて駆け付けたヤンが、台所でビールを飲んでいる息子に話す場面が物凄く良い。
本作には悪さをした男児を叱る場面がここ以外にも何か所か出てくるが、その都度適切な理知を持った大人が正常に機能している場合の安心感がある。たとえば自分の唯一血の繋がった息子がこんな言動をする男に育ったら、これは結構大きな教育と言語の問題だ。
語られる言葉の向こうに見える織り上げられてきたこの物語、彼の人生、そして彼女の人生が思われるところの綾と厚みの豊かさ、設定や展開があるからこそ響く一言一句は、これ以前にこの作品が積み上げてきたものの読者にだから受け取ることの出来る魅力だ。小説とは文章による物語作品であることの魅力を誠実に体現したような場面で、佐藤亜紀は非常に優れた小説家なのだとはっきりと分かる。
普段の作品には見られない地の文の扱い方や口語体の軽さなどが散見するので、この長台詞は旧時代的な作為の一貫とも思えるが、こんなにも誰かを思いながら言葉数を割いて諭す誠実な登場人物を佐藤亜紀作品では初めて見た。温かさと厳しさと悲しさがあって、私はこの場面がとても好きだ。こういう本が自分の部屋にあって、いつでも開ける、というのは気持ちがいいものだと思う。
本作の温かさ、牧歌性、人間性と知性の優位
天才でエゴイスト、誰も彼女には手が届かない、という祝辞が本作には贈られていて、これは確かに読みたいと思わせる魅力的な文句だ。本作のように尖りがなく読まれやすい作品を作者がやっと書いてくれたのだから、商業的な売り文句を使ってでもこれを売りたいと思った人間がいたのなら、その行為は正しい。ただ偽りや誇張の宣伝文句は落胆も生む、宣伝や書評はここが難しい。
では本作の魅力を言い切る場合に正しい語句はどんなものなのか、それは非常に難しい。
ヤケネにも本作にも圧倒的な温かさがある。
家業にまつわる帳簿は見て経営や展望に助言をくれる。ペギン会に関わる子供たちへの教育にも熱心。働いている母親を持つ家庭の子供に肩代わりをしながら教育をしてやるし、女たちが手に職を持てるよう思案したり、役職付きの安心を説いたり、女の生涯を案じている。世を捨てたわけでもない、救貧院に余る人手についてもその活用を模索する。
男の名前でなければ論文も通らない。男の名前なら通る。双子、性別が違うだけで弟なら許されることが山ほどある。そのことに関して、それ以外のことに関しても、ヤケネは自身の感情の多くを吐露せずに見せない、絶えず軽やかに明るく存在している。
ファムファタールは私利の為に男を振り回す悪女にも近いが、本作のかの女性は、他者や知性に対し圧倒的に温かい。この温かさと深淵なる知恵の探求は、徹夜と畑仕事や翻訳とウサギの落差や多彩に富みながら、後輩や続く者たちへの温かさとして循環していく。
本作には女が子を産み継いでいく先、レースを編み繋いでいった先に見える、生産性と未来の希望がある。この温かさは、ペギン会やヤケネが許されるような、この地域の牧歌性と、外を回してくれるヤンという存在があったからとも言える。状況を汲んで役割を全うし、娘がペギンになると言っても止めない、家業や様々な感謝へ報いるために誠実に仕事し理知的に暮らすヤンという信頼に足る男を彼女は得た。彼女は子供も家業も放り出して自分の興味に没頭し、小さな寄り合いから大きな社会への貢献を惜しみなく続けられた。
確かにその時代は、女がその名前で論文も博士号も出版も適わない。彼女は時代と性別に恵まれなかった、けれど家族と男には恵まれた。
幼少期の彼女を認めない両親のもとに生まれ、理解者の弟と信奉者の男に恵まれず、通常通り他家のつまらない男に嫁ぎ、子を産まされ育てて家を切り盛りする役割に押し込められていたのだとしたら、それでも彼女はその困難を撥ねのけて、その天性や知性を活躍させることが出来たのか。こうしたヒロイック的な虚構の躍動は商業ではよく書かれるが、本作では採用していない。ここに、なぜファムファタールという双方に受態的な要素を採用したのか、の視点が入ってくる。
運命のロジック
運命の女とは、それを尊重する理知を持たない男性性や暴力や権力で獲得する男性性には訪れない福音で、そういう人類や無秩序にも生まれない虚構性であり建設性だ。その中で暮らしていける女は幸せだし、手仕事や自分なりの納得や自活の上で生活し、選べる時には男も妊娠も選べる、その自由がペギン会の女にはある、ということそれ自体はずっと求められてきた自由で喜びであり、そんな喜びすら容易くなかった、という価値観の韻を踏む。
悪さをすれば叱られる、賢明なる知性が尊重される、理知的な正しさが向かうその方向性に価値がある。『黄金列車』が人生を諦めた男の悲哀なら本作は、信頼と尊重に恵まれて暮らせた女だから為せた仕事の幸せや建設性がある。調和のとれた世界と、生まれて増えて暮らしていく人類の豊かさ、その希望性があるし、生命の喜びと自然がある。
パリから反乱の香りが漂う終盤は、いつこの地の商業とペギンが襲われる血みどろ始まるのではないかと恐怖したが、本作が最後までその温かさを崩さなかったのは、共和国軍が到達する波乱をプロットに持ちながらも、先に仕込んだフィクションによる大立ち回りを挟むことで、ベギン会や女すら荒らされることなく済むこの地方の無事による。
この奇跡的な成り立ちは、きわめてご都合主義で、ある意味で持たざる者や損なわれるものに対して愛に満ち過ぎているし、愚者に厳しく、現実性に対に対し虚構性が強い。しかしその作為は破綻なく円満な終結をしていて、そこの作為性が本作の肝ではないのかと私は考える。その為の牧歌的な地域選択とベギン会や賢明な女と誠実な男によるファムファタールの素材選択が為された。
題名はモーツァルトのモネット『踊れ、喜べ、幸いなる魂よ』からということらしいが、音楽を含めた多くの造詣に浅い私には結びつきの意図に理解が及ばない様々な教養的文章が本作にはちりばめられており、牧歌的な教養と、その時代における先鋭的な予見の鋭さと豊かさを感じさせ、語りすぎない中にも、しっかりと知の塊が向こうにあることを感じさせる。
商売の発展や危機感とは面白いもので、確率論も天体観測、ウサギの繁殖と番いも、翻訳から惑星、湯がいた人参とレース織り、林檎や農作業、手仕事も雇用も革命も、世界の成り立ち、調和の一部であり、それは自然と唯物論にもよる。かと思えば教養や文体の知性は目に見えず、愚息には及びもつかずに醜態を晒す。ヴォルテールの啓蒙主義的な要素、人間の理性や自由について、そして知性について、あるいは十八世紀という時期に、修道女でもないペギン会の女性たちが歌いながら広場に練り歩いて来る様は戯曲的であり、現実性とは離れたオペラ的な要素で円満まで導いており、そして女の大合唱が許された。この教養的な調和は、物語的な円満作用にも近く、本作の印象を強める要素となっている。
本作にはいつもの歴史的な重さが無い替わりに、教養的な軽さや明るさが随所に配置されており、探求するヤケネの賢さと温かさの円環が、本作を軽やかで晴れやかな明るさで満たし、温かく、優しく、愛しい牧歌性による信頼と円満の調和で満たす、そして続く未来すら思わせる。
作り上げることの難しさをこうも簡単に書き上げてしまった本作は、物凄く作為により成り立っていて、それにより作品性が損なわれることもない。またしてもその教養による調和、作為による円満の軽やかな達成に気づく受け手の素養が必要ともいえるし、一見すると何が書かれたかもわからないほどに上品に仕上げられているところに佐藤亜紀の凄みと深遠がある。分かり易い歴史の重みとはまた別の、教養の明るさで組み上げられた本作は、楽しみ易い簡単な読書に見せかけた渾身の意欲作だ。
そもそも運命の女なんて男の勘違いにすぎない。思い込みや尊重が恋をすることには必要な才能で、その憧憬を支えるのは信頼や当人次第なところがある、それは虚構性を楽しむことにも理知的な判断にも似る。恋の価値と勘違いの幻想は、虚構性の価値と幻想性に通じる。
虚構と作為を楽しむ価値、色気的な意味でのそれは佐藤亜紀的な教養と芸術などの虚構性の魅力であり、つまり本作は、その味わいを胸に抱えるということが単一や複数にとって何であるか、その愉悦の価値性と言える。魅力的な虚構や戯曲性がなんのために存在するのか、これは佐藤亜紀論でもあるし、ファムファタール論でもある。そしてその価値の証明であり、本作自体だ。
予備知識なくても誰もが楽しめる、と私は本稿の序盤で書いたが、従来の著者の作品には絶対に言えない感想を書いて、読み返した自分が一番驚いた。全く異なる作品群を書いて来た著者が、これほど明るい調和に満ちた軽やかな世界を描いた本作が、しかもこの水準で仕上がることの作家性と展開に驚くとともに、重さと暗さの『黄金列車』と軽さと明るさの『喜べ、幸いなる魂よ』の極端な二作を読めることで、この著者の幅と力強さをぜひ感じてもらいたい。

おひさまのランキング登山、こつこつ
登頂まで応援よろしくお願いします🌞
⬇️1日1クリックまで🙇♀️☀️
小説ランキング
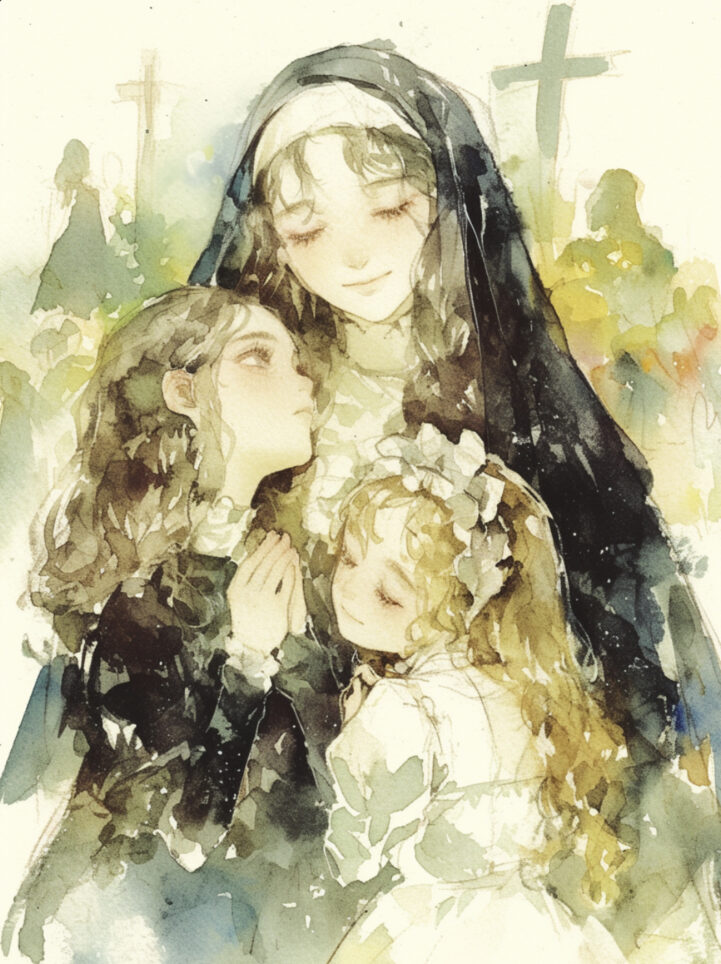



コメント
I’m extremely inspired together with your writing skills as
smartly as with the structure on your weblog. Is
that this a paid topic or did you customize it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it is uncommon to peer a great
weblog like this one today. TikTok ManyChat!