2025年上半期の芥川賞、直木賞は該当作品無しとして話題になりました。良い決断と話題性だなと。
普段読書をしない人が「芥川賞受賞作だから読もうかな」「この作家が直木賞獲ったなら読もうかな」と受賞を理由に読んでみて、「何これつまらない!」「芥川賞作家・直木賞作品って大したことない…」思われる落胆の経験、あると思います。でも時間もお金も期待した純粋な気持ちも返ってこない、それは一読者として悪夢のようです。
ただ、受賞作を読んで落胆しその作家を知った気になるのも少し早い、受賞作以上にも面白い作品を描いている可能性、何作か読んで見えてくるその作家の真価をこそ掴めるものがあるはず。複合的に読む意思がある場合、直木賞芥川賞のような有名体系性を軸に読むことには比較的わかりやすい価値があるのかなと。
近年では注目度や商業性で本屋大賞やこのミスに押され気味な芥川賞・直木賞ではありますが、その歴代作品や作家の信頼や評価はどれほどで、その真価はどこにあるのか? その一覧性や体系を作り出すそのものの価値を現代において思索し尊重することで発展する読書習慣や文化もあるのではないか?
現在は芥川賞で類似企画進行中☀️
毎週水曜に芥川賞企画、土曜にビジネス書や海外文学などを更新。


このスタートを皮切りに、2か月くらいで何作か読んで、受賞作が当たりだった作品もいくつかありました。おすすめ順で以下。懐かしい作家に久しぶりに触れる機会にも、新しい作家に出会う機会にもなりました。直木賞企画第二弾も予定中。あなたの直木賞当たり・失敗経験は?
歴代受賞作は中盤以降になるので、そちらが気になる方は飛んでください。
※随時更新中。サブ的役割のページになるので、ブックマーク推奨🙌何度も戻って来て一緒に直木賞を楽しみましょう😊




エドヴィージ・ダンティカで助産師モチーフが不発だったので、主人公の母親が助産院を開業している『ふがいない僕は空を見た』(2010)を思い出し、検索すると著者が2022年直木賞作家になってい。受賞作を読んだらびっくりするくらいつまらなかったので、選考委員の選評を見たり、歴代受賞作を読んでみよう活動が始動しそうなのでその展望をぜひ!
直木賞はその作家のつまらない作品にあげるものなのか?スタートは窪美澄
著者経歴・デビューから直木賞まで
2009年「ミクマリ」で第8回R-18文学賞大賞を受賞し小説家デビュー。
2010年「ミクマリ」収録作『ふがいない僕は空を見た』出版(新潮社)
2011年『ふがいない僕は空を見た』で第24回山本周五郎賞受賞、第8回本屋大賞第2位
2012年、タナダユキ監督により映画化、第37回トロント国際映画祭に出品
2012年『晴天の迷いクジラ』第3回山田風太郎賞受賞
2018年『じっと手を見る』第159回直木賞候補
2019年『トリニティ』第161回直木賞候補、第36回織田作之助賞受賞
2022年、『夜に星を放つ』で第167回直木賞受賞
デビューこそ華々しいし、次作までは周囲の期待値や評価も高かった様子、それでも直木賞受賞には12年がかかった。その間は何があったのだろうか。『晴天の迷いクジラ』『トリニティ』が見たことある題名だが未読。確かこの前後くらいで、湊かなえや他誰かなど、ドラマ脚本やフリーライター等他業種を経験後小説家デビューして活躍するエンタメ的作家が目立っていた印象があったが、1965年生まれの著者もライター経験後妊娠出産を経て44歳で文芸デビュー、現在59歳、直木賞は57歳で受賞。
(同時期の活躍で言うと沼田まほかるも湊かなえのイヤミㇲ関連で目立っていて『9月が永遠に続けば』『彼女がその名を知らない鳥たち』映画化もされて、個人的には印象が強い)
デビュー後16年間で23作と多作。多数の出版社からの出版歴が凄いし、結果的に直木賞を受賞しているのが文芸春秋というのも気持ち悪い。映像化は意外にも2010年の『不甲斐ない僕は空を見た』の映画化、2017年の『やめるときも、すこやかなるときも』のドラマ化のみ。
私が読書していない間の10年間で聞こえてきたタイトルも少ないし、不作だったのだと思うけどどうのかわからず、市場性が案外当たる読書メーターの感想登録数で見てみた。
単なる読書アプリではあるが現在もアクティブユーザーが多い印象の読書メーターは、結構玄人的な感想も目立ちながらも、気軽な読書趣味の母数の広さから作品につく感想数(=既読者数)から読者市場も垣間見ることが出来るツールに感じるので、あくまで読者数の把握にのみ役立つ認識で、作家や作品の受け取られ方を知りたい時は著者の名前で検索すると面白い。
窪美澄で検索すると出てくる上位はデビュー作が抜きんでており、2位が直木賞受賞作『夜に星を放つ』、3位が第二作目の『晴天の迷いクジラ』、とデビュー作以降はそれほどでもなかった感じが伺える。本屋大賞ノミネートは初回だけだったのだろうか?それはまた今度。
ちなみに最近カフェで二十歳前後の若い子が『さよなら、ニルヴァーナ』読んでいるのを見かけました、愛しい。

花丸デビュー作『ふがいない僕は空を見た』
私が既読なのは『ふがいない僕は空を見た』のみで2012年にすぐさま映画化もされている、
受賞作品の短篇を発端に長編まで練り上げる構想は素晴らしいし、直木賞よりも受賞作品の信頼に足るイメージのある山本周五郎賞を受賞とのこと。
- ミクマリ
- 世界ヲ覆フ蜘蛛ノ糸
- 2035年のオーガズム
- セイタカアワダチソウの空
- 花粉・受粉
まず各章のタイトルも趣向が凝らされていて面白いし、商業的な要素としてはエロ要素、犯罪的な要素、歳の差不倫や思春期の恋心や夫婦の性生活の不穏さはロリコン男性などスキャンダル要素も多いし、それぞれの人物造形やテーマも込み入っていて、文章も悪くなく、面白かった記憶があったので二十歳前後で読んだので記憶がおぼろげだったので再読してみた。
例えば思春期のいびつさ、不妊治療やセックスレス、夫に満たされない思い、満たされない女の承認欲求や欲求不満、主婦の社会性や現代的なネット要素の自由と拡大、同い年の友だちとの視座と狭い人間関係の興味と葛藤、やはり密度。
日本で言うところの中間小説としての魅力や重さは十分に備えている、デビュー作なのが信じられない作品。
つまらなかった直木賞受賞作『夜に星を放つ』
短篇集。コロナ禍にまつわる作品が頭、東京大空襲に関する作品がお尻に詰めていて、そこで社会性や重さを足してみたけれど練り方としてはいまいちなのでほとんど安っぽいだけで終わっている。マッチングアプリで不倫男に騙されたり(真夜中のアボカド)、少年心から年上への憧れ的な海辺と老婆への心配(銀紙色のアンタレス)、母親の幽霊が見えるようになった中学生はいじめられていて(真珠星スピカ)、妻と娘にフロリダに逃げられた男は隣に越してきたシングルマザーとその娘に逃避現実を夢見るし(湿りの海)、父親の再婚相手の女とその稚児との関係と勝手に財布から抜いた1000円(星の随に)、等の関連性も読み応えも感じない作品群。220ページが一瞬で終わる内容の薄さ。後半2編は不穏な要素で興味を引くが、それ以上の何かもなければ短篇の切れも特には感じないし、デビュー作から著者の魅力かと思われた練り上げるような力強さや緻密さは感じない。
個人的に私は作家も社会人も人生も、成長性や発展や展開が大事だと思っていて、勿論最高傑作があるのは仕方ないし、創作における客観性も難易度なら、テーマモチーフのセンスも作品ごとなので、出来不出来があるのは仕方ないにせよ、その創作上の客観性や出来栄えの自己満足は常に更新されて保たれるべきであるし、それ以降は姿勢と向上心の緩みか極まりによってしまうのではないか、というのは理論的な価値観ではあるけど、そのようにして見てしまう。作家は自己の創作が全てになりがちだが、読者という他者はひとりの著作列だけでなく多数の中で比較するし、その作家の生きる時間軸は膨大で、発表されたからには残り、比べられ続ける。それを認識し、少なくとも自分の過去作の中で最良や、せめて多彩だと思えるまで磨き、書き上げた作品の自信はあるのか、一度は問うて内心に求めてもらいたいし、そのようにして新作を出し続ける作家だから現代の読者の信頼を勝ち得る。
処女作が魅力的な個性を映すのは仕方ない、若い未熟な鮮烈さや冒険があることも多いだろう、けれどせめて実力や完成度では経験値と自負を見せてもらいたい。この著者はデビュー作より10年以上後に書いた作品の方が面白い、と言う読者が1人でもいるのだろうか? 私はそんな可能性は感じない。
受賞作は何が評価されたのか? 選評を読む
浅田次郎「どの短篇も一人称一視点でありながら、それぞれの苦悩が書き分けられ、いわば宇宙に生きる人々の不幸の諸相を、的確にドラマチックに、たとえばめくるめく星座のように描き上げた。過剰な小説ばかりの昨今、豊かな文学性を感じた作品は久しぶりである。」
三浦しをん「受賞に異論はない。」「なぜ一番には推さなかったかといえば、各編ごとになにが書かれているかが明確で(丁寧さゆえだが)、「これはいったいなんの話だったんだろう」と読者が想像する余地が少ない=短編としてはややキレに欠けるかなと思ったためだ。また、「真珠星スピカ」の幽霊を、どこまで「(作中において)リアルなもの」と受け取っていいのか、少々判断に迷った。」に異論はない。」
高村薫「作者はすでに十分な手練れであり、これまでの作品と比べて本作で特段何かが進化したというのではないが、描かれる日常はどれも粒がそろっており、そのぬるい毒と醒めた停滞は、現代を生きる大人の鑑賞に耐える。」
無難。その読書から受けた感慨なんてほとんどないんだろうなという感じ。
ちなみにふがいない僕は空を見たでは、いいことを言ってる
浅田次郎「随所で山場を迎えても毅然として動じず、近視眼的な描写もなく、常に物語の全体像を見失っていない。この冷静さは何としたことであろうか。」「貧乏や飢渇や病が、正確に描き出されている」
北村薫「救いのない題材を扱っても不思議に清新である。登場人物が、借り物の知識の絵具で描かれていない。驚くべき力量だ。」「性犯罪を軽々しく扱う新人もいるなかで、田岡さんの造形などの人間を見る力は出色である。小説家が、ここにいる。」「受賞に異論のあろう筈がない。」
小池真理子「(引用者注:「民宿雪国」と共に)二作を強く推すつもりで選考会に臨んだ。」「群を抜いている。図抜けた才能である。驚いた。」「どの章にも救いがたい陰惨さが漂う。~完璧な文章力に引きずられ、読むほどに、作品宇宙がどんどん澄み渡っていくのが感じられた。」
重松清「作品と作者の美点はいくつもあるのだが、なにより惹かれたのは、どうしようもなさをそれぞれに抱えた登場人物一人ひとりへの作者のまなざしだった。救いはしない。かばうわけでもない。彼らや彼女たちを、ただ、認める。」「ただ生きて、ただここに在る――「ただ」の愚かしさと愛おしさとを作者は等分に見つめ、まるごと肯定する。その覚悟に満ちたまなざしの深さと強さに、それこそ、ただただ圧倒されたのである。」
篠田節子「選考委員として様々な作品に接した八年間に、訓練や経験では習得不可能な小説家としての天賦の才が確かにあるのではないか、と感じる作品に出会うことが、幾度もあった。」「第一章を読み始めたときに感じたものも、人の心の有り様を捕らえる感覚と、それを小説として表現するに当たっての恐るべき才気だった。」
5人中4人が二重丸、褒めまくっている、何だよそれ、あげとけよ、デビュー作で受賞したっていいじゃんね、それが作家のためにならないのかは先を見ないと分からないにせよ、賞の信頼はそれで高まるのにね。と思ったら上のは山本周五郎賞の選評だった……ますます信頼が高まる。
選考委員の顔ぶれが一緒過ぎて困惑。
つまらない可能性が高い歴代受賞作を読んでみよう!
最近の受賞作を見てみると、いかに私が最近の作家を知らないかを痛感。中には名前は見たことあるなという人もいたりして、印象と共に、やはり軽く見た限りでも受賞作より面白そうな作品が著作列に見つかる作家さんばかりで、何人か当たりたくなる。
一応日本の中間小説的作家を体系的に読める機会にもなるし、代表作どころ良作とすらいえない作品を受賞作に選んでいる可能性が高いとしても、作家単位ではある程度の水準を満たしているだろうし、どう転んでも現代の作家・作品を読める可能性があるこの企画、面白くなってきました。
2024年 一穂ミチ『ツミデミック』
出世作らしい『スモールワールズ』見たことあるし、『恋とか愛とかやさしさなら』xでよく流れていた。BL作家出身というのも最近の作家さんという感じ。トレンドや文芸の在り方、商業の掴み方が変わってきているんだろうなと言うのも感じる。本屋大賞のイメージが強い作家が直木賞を受賞するという融合、現代的で商業性がある作家・作品が牽引していく強さの文化性について、読者の読書、業界や本質的な意味とは? 現代的な読書や作品から離れている私の読書・当ブログの感覚からしてぜひ読みたい作家さん。
2023年下 河崎秋子『ともぐい』
受賞作、題名みたことある気がする。秋子と言えば私は絲山秋子なんだけどあの人はどうなったんだろう。受賞作、明治の北海道で熊狩にまつわる話らしく、著者は羊飼いを卒業して小説家デビューした?らしい流れを読めるエッセイ『私の最後の羊が死んだ』が目を引き過ぎる。
直木賞企画をスタートさせてから、面白かった直木賞リストで名前を見ることが増えたので、これも当たりの作家作品だという予感がある。
ほらほら絲山秋子も面白そう。
芥川賞系だけどタイトルが良いし、昔からなんだか装丁が良いんですよ、内側のセンスある人が売りたい作家なのがわかる、『ニート』の装丁良すぎる。
2023年下 万城目学『八月の御所グラウンド』
森見登美彦の二番煎じみたいな印象で未読だけど映画『プリンセス・トヨトミ』を観てがっかりしかなかったから未読を貫くことにしたイメージの作家、本家より先に直木賞をとったのかと驚いた。森見登美彦の小説家としての才能は日本的でありつつ日本的で無い感じが物凄くポップで、好みではないけど評価していたけど、その後全然聞かないしあれは不発だったのか。その上で仮に万城目さんのが現在は活躍されているのだとすれば、何事も退場せずに継続することにしか結果はついてこない、良い教訓と悲しみを感じる。
『鹿男あをによし』『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』何がなんでも成功したい生命力は感じる。
『夜は短し歩けよ乙女』『太陽の塔』からの『太陽の乙女』ですからね、パッケージセンス。エッセイは気持ち悪そうで読みません。
2023年上 永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』
全く知らない作家名が出てきた。時代小説?
普段から時代小説書いてる人で一安心。受賞後第1作の『秘仏の扉』が意欲作ぽくて好感。『花に影 令嬢は帝都に謎を追う』もポップな感じでミステリ風味な感じが好感。
2023年上 垣根涼介『極楽征夷大将軍』
『君たちに明日はない』を読んだことある気がするけど、脱落したかなんなのかまったく覚えていない。題名からして受賞作は歴史小説?
普段時代小説主流じゃないくせに、直木賞にチューンナップして時代小説で受賞しに来た感じの人は漏れなく全員嫌いになりそうだけど、こちらは近年は歴史小説を書いている感じもする。ミステリー、時代、歴史、SF、わかりやすいジャンル小説かいい話系癒し系しかもうだめなのか。
著作列、目を引くものは特になし。
2022年下 小川哲『地図と拳』
全く聞いたことない作家名その2.私が無知なだけで、読書界隈では有名な人でありますように。題名のセンスは感じない。
と思い検索するとなるほど、装丁にもタイトルにも力入ってるし、売れ筋と言われたらせそんな感じする。題名は受賞作が地味なだけ、『君が手にするはずだった黄金について』はxでもよく流れていた気がする。
2022年下 千早茜『しろがねの葉』
かつてデビュー作を読んで、その後1.2冊読んで程度が知れたなと思ってから読んでいないけど、才能や期待値は感じた作家が受賞していたと知れて嬉しかった。ファンタジックで非現実的な要素と人物造形や心理描写の不思議な濃さは、だからこそ童話や謎方向に迷走したきっかけにも感じるが、時代小説の中に落とし込んだのであればそれは正道かもしれないと思うので一旦良し。化けていて、成長性を感じられたらうれしい。『雷と走る』もxで流れていたの見た気がする、装丁の力が入っていて良い。


2022年上 窪美澄『夜に星を放つ』
作品を読んでから一覧に見つけるとげんなりする。
2021年下 今村翔吾『塞翁の楯』
誰だろう。これも時代か歴史小説な感じがする。怖い。著者は普段から歴史小説の方で、『雪村を討て』なんて装丁が凄いし、敵側に真田を置くのはセンス。『海を破る者』なんかも大作ぽいが、ラノベみたいな著作列も目立つ。
2021年下 米澤穂信『黒牢城』
この人有名だよね、あのイラストポップな『いちごタルト事件』でしょ!と思ったけど、世間的には『満願』の作者なのかな? 積極性を感じて好印象ではあったけど、時代小説で獲りにいった感じがするのは印象減点。作家なら作風を貫いてとってほしい。
2021年上 佐藤究『テスカトリポカ』
誰だろう。SF? SFで直木賞受賞した作品はあるのかな? 受賞作はまさかのメキシコの麻薬捜査系らしい、まさかのラテンアメリカ。
2021年下 澤田瞳子『星落ちて、なお』
知らない方だけど、瞳子がまずセンス、題名も良いが、時代小説や作家が多くないか。
2020年下 西條奈加『心淋し川』
たぶん名前見たことある有名な方な気がするけど、特に読んだことは無し。と思ったら、以下で出る西加奈子さんと勘違い。紛らわしさすごいな?
著者も時代小説を書きながら、現代的な商業要素として、和菓子屋シリーズや隠居すごろく等意欲を感じる。
2020年 馳星周『少年と犬』
名前を見たことはあるけど星周一が浮かんできて、なんか古臭い人というイメージ。少年と犬って、潔さは気になる。深津絵里好きの私がおすすめす妻夫木聡や藤木直人が出るドラマ『スローダンス』の中で、映画監督志望の妻夫木が社会人の後の初監督作品が『オジサンと犬』だった気がする。主題歌の福山雅治もいいんですよ。
犬とソウルメイトだったり陽だまりの天使ソウルメイトⅡだったり馬もいたり、動物好きは伝わってくる。コーマックマッカーシーの『越境』や『すべて美しい馬』を思い出す。受賞作はタイムリーに映画化中。
2019年下 川越宗一『熱源』
まず著者名が古風。作品名は悪くない。
受賞作は樺太アイヌの話らしい。他も、キリシタン大名や異教文化、鄭家と海寇や東インド会社など、ちょっと思想や興味が違う気がする。
2019年上 大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』
ピカタの人?と思ったらピエタでした。癒し系売れ筋かと思っていたけど、受賞作は時代小説みたい。それにしても作品名、なんのこっちゃじゃない?サブタイトル凄いな。
『空に牡丹』とかも明治の花火作りと富国強兵時代の噛み合わせを描く時代小説、面白そう。全体的に装丁が可愛い、作り手に愛される、売ろうとされてる、大事。


2018年下 真藤順丈『宝島』
著者名の下はジュンジョウと読むのだろうか、すごい。
一度見たら忘れられない名前だが知らないので、見たことも聞いたこともない作家さんのはず。創作性は意欲的な感じ。
2018年上 島本理生『ファーストラブ』
意外な名前が直近で受賞していて不思議。結構有名だと思うが未読。 恋愛小説しか書いていない印象があるので興味はなかったが、直木賞は受賞しているのかと思った。受賞作悪くなさそうだし、3つ目の帯に村田沙耶香を発見、タイトルも良い!
2017年下 門井慶喜『銀河鉄道の父』
受賞作は宮沢賢治の生涯をモチーフに、2023年に映画化もされているそう。『家康、江戸を建てる』で江戸ができるまで、『東京、始まる』と繋いで、江戸を壊して東京を建てた辰野金吾を描く、という理性的な創作性は読んでみたい!


2017年上 佐藤正午『月の満ち欠け』
なぜかもう受賞作がいわ岩波少年文庫に入っているのはどういうわけなのだろうか。
2016年下 恩田陸『蜂蜜と遠雷』
この作品名はSNSでもよく見たし、直木賞受賞作という帯文言がなくても売れてる作家さんの印象があるので、もう別に受賞しなくてもいいんじゃないかと思うくらいの作家さんが、当時51歳、デビューから24年で取る、という謎さ。古臭いイメージがあったけど、近年は本屋大賞と両方出入りしていて伸びた作家さんというイメージ。個人的には『チョコレートコスモス』という作品を2006年当時に書店にてジャケ買いして読んだことあるくらいで、きっと根幹の作品は読んでいないのでこれを機に読む機会に恵まれるのは嬉しい。
興味が持てない名前が並んできたので、恩田陸さんで一旦手じまい。9年さかのぼってみればエンタメ・中間作家としては十分じゃないかなと思う。さらに以前でめぼしいので言うと、2016年の荻原浩さんは『月の上の観覧車』でタイトルとじゃけ買いをしたけど記憶には残らず、西加奈子さんは読まれている女性作家さんだなという印象、2012年下半期の朝井リョウは村上春樹並みに拒絶反応があるのでいくらSNSで話題になろうと読む気になれない特別な作家だし、2012年上半期の辻村深月『鍵のない夢を見る』に受賞させたことを根に持っているし(これが恐らく今回の元凶)、2011年の葉室麟は著者の時代小説が好きだが受賞作は惹かれず読まずにいる、くらいか。2007年の桜庭一樹はライトノベル系作家の先駆けで直木賞受賞した上にその受賞作も結構よかったと記憶していて(受賞作だけ既読)あれは良い受賞だったのではないかと思うし、2005年の東野圭吾『容疑者Xの献身』は代表作にばっちり上げている、ミステリーが打ち破っているのが良いし、かつ審査員の誰が東野圭吾を評価し審査できるのか謎だし、それ以前となると作家名・作品名はさらに目が上滑る。1991年に宮城谷昌光を見つけた。
2005年の時点ですでに現在から20年前、当時作家として脂がのっていたとすればその後も活躍していれば名前を大きく聞くはずだが、そういう名前は全然見つからなかった、作家の賞味期限はながいはずだろう、嘆かわしい現状ではないかなとしか思わず。流行作家、中間小説、その意味するところに品格や王道を求めるなら、直木賞がどんな賞であるべきなのかは、文芸の現代商業を考えても読書趣味や人口を考える上でも大事な材料で資本。
時代・歴史小説が多すぎるし、直木賞の立ち位置が微妙すぎる
受賞作、時代小説多すぎないか……
直木場は立場が微妙で、商業やエンタメ的には本屋大賞のほうが強い印象があるし、売れ方で言うとジャンル特化のこのミスのが強いし、現代的な感が全くない時代遅れの埃被りの典型。
現在出版流通する作品の時代・歴史小説が占める割合って分母に対してそれほど大きくないと思うのに、直木賞受賞作に限ってはなぜか時代小説や歴史小説が多いのが不自然だし、ジャンルに偏りがあることは現代的でないことに、主催者側は疑問も懐疑も進展意図も持たないのだろうか?
読者や商業に慮るのが創作の姿勢とは異なるのは分かるけれど、現代人で時代小説や歴史小説を読む層って結構少数派な気がするし、賞の格としては中間小説の中で本格派的な固さみたいなもの欲しいのは分かる。けれど結局は芥川賞との対比で確立するなら時代にあったエンタメ作家に贈るように変革していかないといけない難しさはあるけど、それは芥川賞が現代における文学性の確立や文学を志す作家の後押しをするだけの格であるようにいかに自立するかの課題があるのも変わらないし、変化し生き残れない弱者の地位に落ちて品位の何もない気がする。
同じジャンル小説であっても、ミステリーやSFよりは歴史・時代小説などの方が文学的な要素が入り込む可能性はあるかもしれないけれど、それこそ作品毎だし、それを見極めて読み込むのが読書なら、そこの可能性や醍醐味を否定してジャンルで頭ごなしにする雰囲気の門戸の狭さは、読書という能動のそれ自体を否定する価値観で、極めて遺憾。
直木賞は作家単位に上げるものであり、商業出版の一定水準に満ちたと判断され、中級以上であると認められたら貰えるバッチみたいなもので、一種のクラス替えで成り上がりのような感じで、受賞作がその作家の著作の中で特別優れているとは言えないにもかかわらず、一応賞の知名度はあるので、直木賞受賞作だから面白いかもしれない、と普段小説を読まない層が期待して手に取ってがっかりすると、その作家がもう読まれない可能性もあれば、小説全般の信頼も損ないかねないので、受賞作品+著作列の中で面白そうだと個人的に感じる作品を読むことでいろいろ考えていきたい。
国内における直木賞系も芥川賞系も本屋大賞系も、個人的には本質だとは感じないが、国内文芸や作家を応援することは大事だし、読書人口や商業としては外せないのもわかるので、ある種義務感みたいな気もするが、それにより知ることができる機会にも感じる。新しく良い作家作品を見つけて楽しみたい。
仮にも日本でいちばん有名かつ、書店員が選ぶセールストークやフェスティバル祭典とは別の、業界としての自負や売り出しの価値があるなら、日本文芸の魅力や粋を集める意気はあってほしい。



































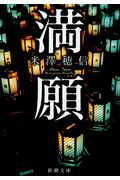




























コメント
エドヴィージ・ダンティカの助産師モチーフが不発だったのは残念ですね。主人公の母親が助産院を開業している『ふがいない僕は空を見た』を思い出しました。直木賞作家の受賞作を読んだのですが、驚くほどつまらなかったです。選考委員の選評や歴代受賞作を読む活動を始めるのは興味深いですね。『夜は短し歩けよ乙女』や『太陽の塔』からの『太陽の乙女』のパッケージセンスはどうでしょうか?
確認、返信が遅れて申し訳ありません。
コメントありがとうございます!
直木賞企画、受賞作や作者について調べたり、選評を読んでみたり、
普段とは違う作品の選び方や読み方をしているので非常に面白いです。
このコメントは、小説や直木賞についての興味深い感想を述べています。自らの読書体験を通じて、選考委員の視点や歴代受賞作に興味を持ち始めたようです。特に『夜は短し歩けよ乙女』や『太陽の塔』の関連作に注目している点が印象的です。しかし、エッセイにはあまり興味がないようで、その点が少し残念ですね。
あなたは、直木賞の選考基準についてどう思いますか?
確認、返信が遅れてしまったので二通目を頂いた感じでしょうか?
大変申し訳ございませんでした、コメントありがとうございます。
エッセイは作品だとは思っておらず、あくまで文筆業で稼げる人間の特権性だと思うので、
虚構創作や文芸が好きな自分からすると畑が違うように感じてしまいます。
文章やその作者への興味が尽きない方からすると、魅力的に感じるものなのかもしれませんね。
いつかエッセイを読みたいと思える方が私にも見つかれば、それは幸福なことだと感じるのかも。
このテキストは興味深いですね。『ふがいない僕は空を見た』についての感想が率直で面白いです。著者が直木賞作家だと知って驚きましたが、受賞作が期待外れだったとのこと。選考委員の選評や歴代受賞作を読んでみる活動が始まりそうで楽しみです。でも、エッセイは読む気になれないとのことですが、なぜそんなに抵抗があるのでしょうか?