書くことの効能や、物語にすることの効果については色々言われるところだと思うが、その生業は夢遊病者やほら吹きのようでもあるし、壮大な夢やちっぽけな愛おしさが、いかに自分の胸を打ち、他人にとっての価値になるのか。たかが文書、たかが物語の、現代における価値について考えながら今回の記事を書いた。
虚構創作や文芸を愛する風情、一生の風景になる憧憬や一瞬の感情が劇的に思える幸福について。
自伝的要素を扱う作家の手つきの愛おしさ
まず題名に惹かれて『たんぽぽのお酒』を読んだ。
著者はレイ・ブラッドベリ、米国のSF作家として代表作の『華氏451度』や『火星年代記』などで有名なので、名前は見知っていたが著作を読むのは初めて。
その読中、かつて読んだフリオ・リャマサーレスの『無声映画のシーン』を思い出して、半自伝的要素について考えたし、それらを作家が扱う時の手つきについて考えていた。形にしようとした所の虚構性と、創作的意識や作為、そして自分にとっての書く意味と、他者が読む意味について考えるのかどうかという所の志向性や他者性について。
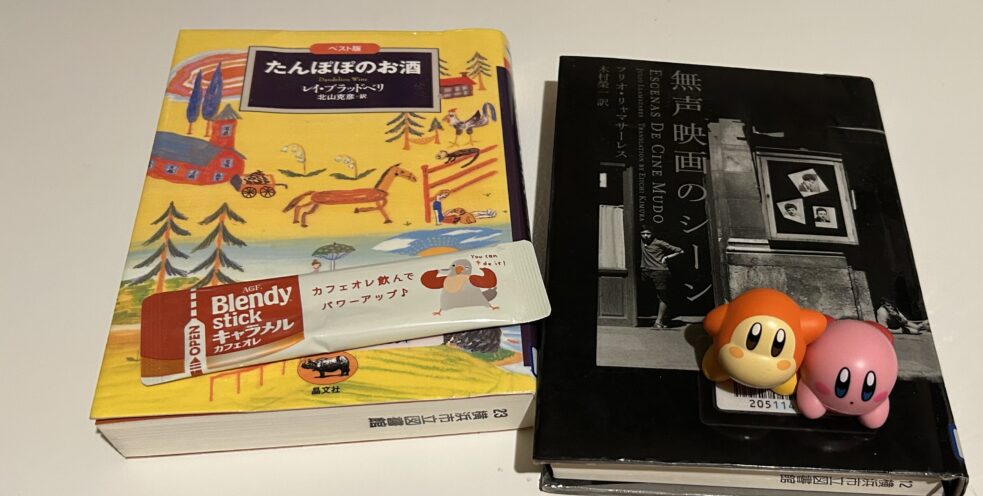
『たんぽぽのお酒』レイ・ブラッドベリ
まず文章が装丁と雰囲気の似たポップアートのファンタージにつき、それだけでも印象が強いので好き嫌いが分かれる気がするし、断片的に語られる対象群と飛躍的な文章はまさに幼年期の輝きと老年期のまどろみで、それもまた作品評価にはなかなか挑みづらい所がある。
ファンタジー世界観で死を扱うことは宮崎駿の『崖の上のポニョ』が浮かんだが、他の脂が乗ったファンタジックな作品は浮かばなかったから、両作とも子供に贈る理性よりは自我が目立つ気もするし、生と死のせめぎ合いまで高めて作り書き上げられていないところに老齢の体力と熱意の底を見を見た気がする。
本作の最後はそのモチーフテーマで上手くくるみ、あたかもこれから生きていく年少者や過ぎ去った彼らに儚いメッセージを送っているかのように閉じているが、その表面にまぶした理性よりも混沌としつつ飛躍した作家自身の自我の方が強く感じた。だいぶ特異な様相をしているので、これが著者の特徴であるなら、それを魅力に感じる読者層の想定は出来る。
「五百、千、二千はあるな。よし、よし、けっこうな量だ。のんびりと摘めよ。すっかり摘むんじゃ。絞り器にかけるひと袋ごと十セントのお駄賃だよ!」
「そいつぁいいや!」
少年たちにこにこしてかがみこんだ。彼らが積んだのは金色の華だ。世界いっぱいにあふれ、芝生から煉瓦の街路へと滴りおちて、水晶のような地下室の窓をそっとたたき、激しくたぎりたって、融けた太陽のまばゆい光ときらめきを四方八方に放っているあの花。
「毎年のことだ」と、おじいさんはいった。「あれは狂ったようにあばれまわる。わたしは勝手にやらしているんだよ。庭に咲くライオンの群れだからな。じっと見つめてごらん、網膜が焦げて穴があくから。ありきたりの花さ。だれも目にとめようとしない雑草だ、たしかに。しかしわしらにとっては、気高いものなんじゃ、たんぽぽは」
そこで、慎重に引き抜かれ、袋に詰められて、たんぽぽは地下に運ばれる。地下室の暗闇は、たんぽぽが到着すると明るく燃えるのだ。ぶどう絞り器が、冷たく、口をあけて立っている。花がどっと投げ入れられると、それが温まる。絞り器は、もとのように口を閉められ、おおじいさんの手でスクリューがぐるぐると回転し、ゆっくりと作物を押しつぶす。
「ほら……ね……」
金色の潮流、澄みきって晴れあがったこの六月のエキスが流れ出し、ついで下の受け口からほとばしると、それを甕に入れ、酵母をすくいとり、清潔なケチャップのふりかけ容器につめて、こんどは地下室のうす暗いところにきらきら光る列を作って並ばせるのだ。
たんぽぽのお酒。
この言葉を口にすると舌に夏の味がする。名都を捕まえてびんに詰めたのがこのお酒だ。それにダグラスが、自分が生きていることを知り、ほんとうに知って、世界を転がりまわってそれをすっかり、膚で目で感じとったいま、彼のこの新しい認識の幾らかを、この特別の収穫日のいくぶんかを、封じこめてとっておき、雪が降りしきり、何習慣も何か月間も太陽をおがむこともなく、おそらくはあの奇跡のいくぶんかはすでに忘れさられて、再生を必要としている一月の日に開けられるようにしておくことこそ、ふさわしい、適切なことなのであった。今年は推測もつかないほど驚異の夏になろうとしているのだから、彼はそれを全部しまっておいて、ラベルを貼っておこうと思う。いつでも望むときに、このじめじめしたうす暗がりのなかへ足音をしのばせて降りてきて、指先を伸ばせばいいように。
するとそこに、何列も何列も、朝に開いた花がそっときらめき、わずかに積もった埃の膜を通してこの六月の太陽の光が輝く、たんぽぽのお酒が並んでいるのだ。それを透かして冬の日をじっと凝視してみるといい――雪はとけて草が現れ、樹々には、鳥や、葉や、花がもどってきて、大陸いっぱいの蝶々のように、風にそよぐのだ。またそれを透かして見れば、鉄色の空が青く変わるのがわかるだろう。
p25
「愛の本質はこころだといつもわかっていましたよ。たとえ肉体がときにこの認識を拒絶することがあっても。肉体はそれだけで生きているんです。食事をし、夜を待つだけの為にそれは生きているのですよ。本質的に夜のものなのね。でも、太陽から生まれたこころのほうはどうなの、ウィリアム? 一生のうち何千時間となく、目覚めて、意識しながら過ごさなきゃならないのよ。あなたは、あのみじめで利己的な夜のものである肉体を、太陽と知性の全生涯につりあわせることができて? わたしはわからないわ。わたしがわかるのはただ、ここにあなたのこころがあり、ここにわたしのこころがあって、ともに過ごした午後にくらべるべきものはわたしの記憶にないということね。まだたくさん話すことはあるけど、別のときにとっておかなきゃ」
「もうあまり時間はないようですがね」
「そうね、でもおそらくきっとまた別の機会はあることでしょうよ。時間はとても不思議なもので、人生はその二倍も不思議だわ。歯車が欠け、車輪がまわり、人生が交錯するのも早すぎたりおそすぎたり。わたしは長く生きすぎました、それだけはたしかね。そしてあなたは生まれるのが早すぎたか、おそすぎたかのどちらかだわ。ちょっとしたタイミングがおそろしいものね。でもたぶんわたしは愚かな娘だった罰をうけているのよ。とにかく、次のもう一回転したときは、車輪はふたたびうまく働くかもしれないわ。そのあいだにあなたはいい娘さんを見つけて、結婚して、幸せにならなければいけないわ。ただひとつわたしに約束してもらいたいの」
「なんなりとも」
「歳を過ぎるまで生きないと約束してほしいのよ、ウィリアム。少しでも都合がよかったら、五十歳になるまでに死になさい。少しばかりのおこないが要るかもしれないわね。でも、私がこんな忠告をするのは、ただただ、いつまた別のヘレン・ルーミスが生まれてくるやもしれないからなのね。あなはたそれはそれは長生きして、一九九九年のある午後に本通りを歩いてゆくと、そこに、二十一歳のわらいが立っているのを見つけて、またすべてがバランスを失ったら、おそろしいことじゃないの? どんなに楽しくとも、わたしたちが過ごしたような午後を、またこれ以上経験することはできないと思うのだけど、あなたはどう? 一緒に千ガロンのお茶を飲み、ビスケットを五百も食べれば、ひとつの友情には十分だわ。だから、あなたは二十年くらいのあいだに、いつか肺炎に襲われるにきまっているわ。いつまでもあなたを私とは反対側にぐずぐずさせておくつもりなのか、わたしにはわからないのよ。おそらくすぐにあなたをもどしてくれるのでしょう。でも、わたしもできるかぎり、ウィリアム、ほんとにできるかぎり力をつくすわ。そしてすべてがふたたび正常にもどって、バランスがとれたら、何が起こるかわかる?」
p249
こんな文章が永遠に続くこと約四百頁。ところどころ異彩を放つし、幼い瑞々しさも感じるのだが、冗長も冗長、まどろみの中に溶けてしまいそうな退屈さもはらんでいて、添削したくなる口語体が続く。児童文学の体裁を貼って、作品性の幼稚に理由を作ったように感じる。
別に悪くはない、そういう幼稚や純粋と熱さと躍動のある作家なのだろうなと思った、逆に言えば本格生真面目に書いた作品性の著作も気になるところではあるし、児童性を廃した作品の飛躍にも興味はある。往々にして半自伝的作品は、そのほかの著作列とは異なる様相をしているだろうから、その個性はそれぞれ認められるべきなのだろうと思うし、強烈なファンには大衆性に届かなくてもこの場合は問題がない、著者の愛した故郷性があればよいのだから。
『無声映画のシーン』フリオ・リャマサーレス
静謐、という言葉がよく似合う作品にはたまに出会うが、本作は間違いなくその類である。
物語の雄弁さも圧倒的な感情の波も存在しない、写実的とも言っていい。虚構創作としてはどんな魅力を目指した結果、どんな形をしているのかが非常に難しい形をしている。日本語訳の刊行が2012年になっているので、その当時読んだのだと思うので私は22歳前後か。
作者の序文や訳者のあとがきは当時の私も読んでいるのだと思うが、そこでは自伝的要素やフィクション性について触れているが、どちらか片方単一に振れることのないような表現がされている。私はこれを作者の半自伝小説であるし、けれどもとても創作的な作品だと捉えた理由と、『たんぽぽのお酒』と対比して思い出された理由は、その静謐さと、物語としてではなく一枚ずつの写真をもとに当時を思い出して形にするための静かな祈りと復刻の作業であることや、作り上げることや物語の躍動に乗せることなく、ただ思い出したい情動に作家の郷土愛を見た。思い出や視点を遺したい作家の性質も同様だ。
※著者のフィクションが読みたい方は以下。ここまで創作的な作家です。

祈りと復刻の作業、永遠への塗り固め
物語としての虚構性やフィクション性の弱さは『たんぽぽのお酒』とは比べ物にならず、『無声映画のシーン』はただただ静かに1枚ずつの写真の連なりを淡々と描写することで一個の故郷とその時代の立体化に成功している。
翻訳の文章でさえも、ここまで差が出るのかというほど、両者はともに著者の自伝的要素を素材にしているにも関わらず、フィクションとしての躍動と静謐のここまで極端な二作を並べることが出来る半自伝的小説というくくりと作家性の自由とその可能性を見る。読み比べてみると、作家が自分の人生や故郷や子供時代に見出す虚構性と、それを大人になった作家人生の中で一冊に文章化するにあたり試みる作為性の自由度に驚かされることだと思う。それが直結する所は古き良き過去の愛おしさであり、現代や商業や大衆の他者とは多少関係がないし、たとえば『たんぽぽのお酒』のように幼年期のファンタジーに似つかわしくない年老いた少年少女の死への実感とまどろみを隠さないまま作品昇華に至らずしても、出版し読まれる作家の地位や知名度があれば、多くは許されるし求められる。
『無声映画のシーン』だけでいうと、虚構創作として物凄く面白いといった一冊ではない。初読当時の私にはあまりピンと来ず、著者の他の作品も読みたくなるような一冊ではなかった。静かで、どこまでも何も起こらず、断片同士のつながりもよくわからなかった。
けれど今は、このテクニカルを選び、ここまで静かな文章を書く作家の激動の物語表現があるのならば読んでみたい、と思う。つまりは簡単なはじめましての一冊目に読む作品ではなかったと思うし、『たんぽぽのお酒』についても一冊目に選ばれるべきものではなかったかもしれない。
『たんぽぽのお酒』が書き上げない自由の幼稚を児童書という包装にくるんだように、『無声映画のシーン』は作り上げないことを半自伝的要素と結びつけた。
半自伝的小説が代表作になる可能性は低いし、入門の一冊には厳しいと言っているわけでもあるかもしれない。そこには作者の客観視を含むことの出来ない偏愛的な記憶の愛おしさがあり、虚構創作させるだけに魅力的に感じてしまう虚構性が存在していて、それをどれほどテクニカルに扱おうと、偏愛しないように意識すればするほど脚色は難しくなるし、作り上げず書き上げないことの素朴な言い訳も立つ。
全ての個人的感情や憧憬を客観に捨ててしまえば創作など出来なくなるだろうし、作家はある種独善に惹かれて突き進む作品群についてくる読者の需要を掴めばいいだけなので、多くの読書機会を産んできた作家の独善的モチーフとアプローチを発端にした本作の魅力は、さながらその資質の露出と脱力と言えるだろう。自己愛の創出と少なからずの客観性や創作性でまとめ上げた、自慰的行為によるファンサービスに近い。本質的には多くの創作がそのグラデーションの中にあり、作風や著作列の中のさらにまたそれであることにも思い当たる。
作家の人生は全て作品の中に込めることが出来るし、全てが時代の波に乗って流されていく。
おひさまのランキング登山、こつこつ
登頂まで応援よろしくお願いします🌞
↓1日1クリックまで🙇♀️🌞
小説ランキング












コメント