『日の名残り』を読んだとき、この作家はあまり好きではないからもう読まなくていいと思った。
一冊目のその読後感と、当時もう評判で最高傑作だと言われていた『わたしを離さないで』のあらすじを見て、次を読む気になれなかった。十年前のそんなことを思い出しながら、気になる題名だからと手に取った本作。ノーベル文学賞受賞作家であり、世界的にも有名な著書のある現存の作家は、彼以外に何人いるのだろう。受賞後、親を失いながら書いた、その六年間の仕事とは。
ノーベル文学賞受賞後の執筆作品『クララとお日さま』
裕福な家庭の子供には「AF」と呼ばれる人工親友が用意される時代、そして「向上処置」という子供の将来の為の医療的な賭けがある世界。ショーウインドーの中から街を見ていたAFのクララは、ガラスの向こうから声をかけてくれた病弱な少女ジョジ―と出会う。売られていく最新型のAF、何日待っても再会に来てくれないジョジ―、店内に売れ残り続けるAFたちに優しく声をかけてくれる店長さん、自分を欲しいと言ってくれた別の子供に握られた手を握り返せないクララ。
太陽光からエネルギーを得る作りのクララは、店内に飾られて居る時も大きなショーウインドーから入り込むお日さまの陽光や、日差しが作り出す光模様をつぶさに観察しては憧れていた。そんなクララが出会った少女ジョジ―は、自分の家の魅力を語る場面で太陽に言及する。
「ハイ! ね、聞こえる?」と声がガラス越しに聞こえました。
ローザは店長さんの言いつけどおり、正面のRPOビルを見つめています。でも、わたしはいま話しかけられました。ですから、少女の顔をじかに見て笑顔を返し、誘うようにうなずきました。
「ほんとに?」とジョジ―が(そのときはまだ名前を知りませんでしたが)いいました。「自分にも聞こえないくらいの声だったのに、ほんとに?」
わたしがまたうなずくと、ジョジ―は感心したように「ワーオ」と嘆声をあげました。
~~~~~~~~~~~~~
「ね、あなたたち、そんなふうにすわってて暑くならない? 飲み物とかいらないの?」
わたしは首を横に振って、両方の手のひらを上向きにしてもち上げ、降り注ぐお日さまの栄養のすばらしさを伝えました。
「そうか、わたしって考えなし。日に当たるのが大好きなのよね」
~~~~~~~~~~~~~~
「あなたたちのとこからだと、太陽があの大きなビルの後ろに沈むところしか見えないんじゃない? ってことは、ほんとうに沈む場所は見えないわけだ。あのビルがいつも邪魔になるものね」ジョジ―はさっと振り返り、大人たちがまだタクシーの中にいることを確認して、つづけました。「わたしが住んでいるところはね、邪魔になるものが何もないのよ。わたしの部屋から太陽が沈む場所そのものが見える。つまり、夜、寝にいく場所ね」
わたしの驚きが伝わったのでしょうか。ローザがハッと反応する様子が目に端に映りました。店長さんの言いつけも忘れ、ジョジ―をまじまじと見ています。
「でも、朝、登りはじめるところは見えないのよ」とジョジ―が言いました。「そっちには丘や林があって邪魔になる。その辺の事情はここと同じかな。いろんなものがいつも邪魔をするの。でも、夕方は別よ。部屋の窓が面している側はだだっ広いだけで、何にもないから。うちに来て一緒に住むようになれば分かるわ」
大人が一人、そしてもう一人、タクシーから歩道に降りてきました。たぶん物音から察したのでしょう。ジョジ―は振り向かなくてもわかったようで、急に早口になりました。
「誓ってほんとよ。太陽の沈んでいく場所が見えるの」
~~~~
「いかなくちゃ。でも、また来るから、そのときもっと話しましょう。」そして、ほとんどささやくような声で「あなたはどこにもいかないわよね」と言いました。
わたしが笑顔でうなずきました。
「よかった。じゃあ、いまはさよならね。でも、いまだけだからね」
愛しい主人のジョジー、神秘的なお日さまへの崇拝
人工親友であるクララは14歳の少女ジョジーに買われて、彼女のAF(artificial friend?)になってからの大きく小さな冒険と、ジョジーの長く短い10代を描いた作品。
ジョジ―のことはジョジ―、ジョジ―の母親リクシーのことは一人称では母親と認識しながら「奥様」と呼ぶ。この二人を中心に、クララがいたお店の店長さん、一緒に並べられていたローザ、ジョジ―の家の家政婦、隣の家に住むジョジ―の幼馴染の男の子リック、リックの母親ヘレン、ジョジ―とリックの父親たち、肖像画家兼AF研究者のカパルディさん等、本作の登場人物はそれほど多くはない。彼らとの交流と共に物語が展開していく。
物語のすべてはクララの視点から語られる。自分の主人であり唯一の親友になるジョジ―との出会い、彼女を待つ店の中での時間から、彼女のAFとしてお家に連れて帰られてからは、常にそばで暮らす静かな生活を記述していく。
これには色々な効果が強いし、この人称設定の時点で本作の成功はほとんど決定づけられたようなものだ。寓話性から愛のテーマまで、非常に豊かに読める。
隣にあるリックの家に初めて行き彼の母親と話す、ただそれだけの場面、あるいは草原の向こう側に見える納屋に行き、彼女にとっての崇拝に懇願する、ただそれだけの場面が、異様に恐怖に満ちたり圧巻の奇跡な瞬間に思えたりする。子供の背丈のクララが背の高い草原の中を一人で抜けていけないから、リックの背中に乗せてもらって草をかき分けて進む、ただそれだけのことがとても危険な輝きに満ちる。ジョジ―のAFとして店の外に出られた時を除けば初めて街へ行くシーン、それまで自分に対し不穏な雰囲気だったジョジ―の父親という家の外の人間と初めて二人で会話する車内のシーンの緊張と緩和、しばし都会の冒険、なども急に映像映えする場面に思えてはっとするほど、普段のクララの日常は閉じた狭い世界で過ごしている。
AFは子供と常に一緒にいて、病床のジョジ―のAFになったクララは基本的に家からは出ず過ごしているので、ほんの少しの外出やその先での出来事が大冒険の一場面になる効果があり、これが等身大の生命やその魅力を感じさせる。
親が子供の為に買い与える人工知能のはずのクララが、太陽が寝に帰る場所という仕組みを信じるのは科学的に信じがたいし、納屋で休憩しているなどといった寓話的な象徴を信じているところ、太陽光が自分たちに持つ効果と人間に対する効果のほどを勘違いしている点も同様だ。
進んだ文明であるはずが、煙を吐き出す謎の機械が登場する違和感も、環境破壊をする機械がお日さまにとっての諸悪の根源のようにクララが認識していく点なども不可解で、目の前で空気汚染をしているただ一つの機械を壊せばお日さま評価してもらえると信じる正当性の不自然さはどうしても辻褄は合わない。
それはまだ動けるはずのAFを廃屋に捨て置くような扱い方にも思われる。その再利用をすれば、おさがりで型落ちとは言えより多くの子供がAFを持てるし、老後的に老人ホームに送って介護的立場に活用するでもいいし、ゆりかごから墓場まで的なこの再利用は社会感情的にも悪くない活用だと思うけど、そうされない社会的な価値観や常識がどんな創作性なのかを考えると、意図的な感傷に行きつく気がしてならなかった。
クララの勉学的な知能については中盤にリックの母親に勉強の指導を頼まれる場面でも「教科書なんてあなたには、子供の遊びも同然でしょ?」と言及があるように、向上処置という仕組みがある時代の子供のお目付け役に学術的な貯蔵のないパートナーだとは考えにくく、知識の搭載はなされているはずだ。クララは自分が太陽からエネルギーを貰っている点から、知識的な把握に魅力的な虚構性のイメージをかぶせることは勝手だし、ショーウインドーの中からある奇跡を見てさらに拍車がかかっているのだとしても、ジョジーの為に動く時はより現実的な試行錯誤が行われるべきで、その懸命は謎に満ちている。
科学が進歩し、格差が拡大する世界にあって、変わらない愛
クララの視点から語られるからこそ効果的な場面構成や物語性と、しかしそれでは整合性がつかない世界認識は寓話的な創作性で覆い隠している脆さであり、その成立のために不釣り合いな機械を持ち出すところも、少し虚構性が弱い。本作はつまり寓話的な愛の物語であり、人工知能に不釣り合いの妄信性であり、創作的な意図とほころびが錯綜する。
例えば深くは言及されないが、ジョジ―の父親ポールの元職場である工場地帯やそこを追われた理由と現状だとか、多くを語られない店長さんの前後であるとかから伺い知れる、向上処置が産まれた世界観に必ず存在し拡大していくだろう格差社会の全貌を含めて、クララの視点からしか語られることがない本作は、ジョジ―の人工親友である自分の外側の世界に関しては無関心で無知であり、語られすぎない世界の全容についての不穏は、これから大人になりながら生きていくジョジ―の展望について回る世界の不穏であり、子供時代の彼女の友だちには不要なものであり、搭載されていないのかもしれない。ただそれは世界認識、常識的な知識という面でやはり説明がつかない。
そのようにして本作には、その世界観を語りすぎないし、作り上げるに不自然な成立があるが、それを世界観の不穏性として受け取ることで思索の余地を残していて、語りすぎないクララの視野による創作性として技術的な達成と、寓話性の魅力で全体的なまとまりがあるので、そのように読めはする。
そしてその語られない格差社会は、しかし子供たちが生命的な成否を分かつほどの行為への判断を親に迫るような世界だ。
向上措置を施される子供、施されない子供を取り囲む環境が、そのまま大人になってからの格差に繋がるから、再度賭けに出る母親も、恥に気付かず頼み込んで大学に入れたがる母親も、大人になってからの社会を生きる我が子の先を思うからこそ、ある母親は自分のようにしてあげたく、ある母親は自分のようにはならないように、自分にできうる限りのことをして、最善の教育と機会を与えてあげたい。
子供たちの命運を分かつのは向上処置のそれ以上に、どんな経済状態の家庭に生まれ、どんな理知と人間性の母親のもとに生まれるのか、そして恵まれ、はたまた縛られるのか、その命運を二人の子供に与えて対照的に炙り出す。
対照的な二人の父親は、解雇される側、もう片方は特権側として登場する。彼らはあくまで父親という役割パターンの登場としてその外側を伺わせるだけで終わる。クララにとってはジョジ―が世界の多くで全てであり、彼女と共に暮らしている母親はまだしも、別居している生物学上の父親は完全に蚊帳の外に置かれる。ジョジ―と母親、リックと母親、二家族とも隣の家に暮らしており、そこには父親は存在していない。そして草原に囲まれた地域に暮らす二家族は、持つ親と暮らす娘、持たない親と暮らす息子、というテーマ性を明確に映す。
明暗を分けられた父親のパターンはそのままその後のリックを思わせもするし、向上処置を受けた子供も、生き抜いた先にまた生き抜いていかなければならない将来を暗示する。同様に、子供時代の恋人も、その後の優劣により生活圏が異なることによる別離にもさらりと言及されて、彼らが大人になってからも生きていくその世界の明暗を思わせるが、親と処置を持たざる者のリックがそれでも爽やかに今後を見据え、偽りではなかったとそれをクララに謝辞する場面に暗さはなく、むしろ生命観と人間性に満ちており、信じたい愛の魅力がそこにあるのだと思いたかった。
AFを与えられ、向上処置を施されたジョジ―に対し、どちらの経過も持たないまま大人への道を進むリックはジョジ―の相手として置かれるが、蚊帳の外になる父親とは違い、幼馴染のリックはつぶさに観察されて余韻が厚い。クララからジョジ―へのことさらの思いやりがわかるし、通り過ぎていく相手を思わせる儚さがあるし、それはみんな青春だった。
病床に伏せるジョジーを見舞いながら、ジョジ―が絵をかいてリックがそれに台詞をつけるというなんてことない遊びを、強いメッセージ性と印象的な創作性で描いて仕立て上げて見せるところなどは非常に上手い。クララとジョジ―、ジョジーとリックなど、子供同士の世界観を描く時のこの作家の情感の深さや濃さは間違いなく魅力で、これはたぶんこれから読む『わたしを離さないで』でも勿論発揮されたのだろうし、この作家の武器も確信できた。
※これは無残にも裏切られ、打ち砕かれたうえで再構築される
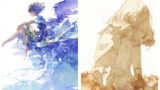
作品の魅力と、作家の弱点
クララの視野の外の世界、少女ジョジーの世界の外側、大人になった彼女が生きていくこの先の世界と、そこに生きる大人達の描き方や世界観が弱く、その点で今一歩である、というのは『日の名残り』を読んだ時の軽さと浅さを思い出すが、本作に限って言えばクララから見た世界の寓話性としてそこは取捨していい部分であるし、語る人称と語られない部分については創作性として許される。
しかし確固とした世界観の確立があってからの描写で導くには、もう少し硬さや深さによる安定感があっていいと思うし、どこかしら浅いし何かしら薄く感じるのはその前提の脆さのせいだろうと思う。人物に関しては作者にとっての大人や人間は、この程度の興味の解像度と認識なのだろうなに留まるに過ぎず、子供時代の幼さや青さの情感といったものへの憧憬との落差が大きく、魅力的な子供は書けても、大人や、それが属する世界は書けないのではないかとの懸念が残る。
本作は、クララが語る物語だ。クララが語ることのない部分の魅力と深さが、語られないままにも感じさせるかどうかの人称問題がそのまま本作の評価軸になるのではないかなと個人的には思う、その意味では若干非ではあるが、クララが語る部分を寓話性であてはめた創作的な魅力の模索と、主人公に据えた子供の世界の狭さを魅力的描いた作品性を思えば、本作の評価としては是でもある。
ジョジ―の出発直前の数日間は、緊張と興奮の毎日でした。メラニアさんがまだ家にいたら、万事はもう少し落ち着いていたかもしれません。でも、新しい家政婦さんには、やるべきことをぎりぎりまで引き延ばし、最後の瞬間にいくつかまとめて一気にやろうとする癖があって、それがびりびりした雰囲気に一役買っていたような気がします。私はとにかく邪魔をしないことをモットーに、なるべく物置から出ないようにし、ジョジ―がつくってくれた踏み台にのって小さな高窓から野原を見たり、家の周りで起こるいろいろな物音に耳を澄ましたりして過ごしました。
~~~~~
「では、クララ、教えてくれる? あなたはあれ以来、ここに来るまでずっと、あなたを買ってくれた人たちと一緒だったのかしら。こんなことを聞いてごめんなさいね。わたし、今はもうそういう情報にアクセスできないものだから」
「構いません。はい、(ネタバレ・割愛)まで、ずっとジョジ―と一緒でした」
「では、大成功ですね、いい家だったのですね」
「はい、できるサービスをすべて提供して、ジョジ―がさびしがるのを防ぎました」
「あなたならそうでしょう、あなたのおかげで、その子は孤独の意味さえ知らずに済んだでしょう」
「そう願っています」
~~~~~~~~~
「お帰りになるまえに、店長さん、もう一つご報告することがあります。お日さまはわたしにとても親切でした。最初から親切でしたが、ジョジ―のところにいるときは輪をかけて。店長さんにはぜひお知らせしておかねばと思いました」
「そう? 太陽はあなたにいつもよくしてくれたのね、クララ」
クララはお日さまについての報告をするが、店長は太陽について返すし、その後たった一文で、ある女性の長い人生の悲哀と豊かさを思わせてしまうのだから、小説家としての技術があることは疑いようはない。このあとクララはジョジ―にまつわる愛について語るが、多少語らせすぎだと思うがゆえにその先を思わせる。
本書には、人工親友の主人への愛、初恋、母親から子供、子供から母親、父親から娘へ、あるいは息子へ、家政婦から雇い主へ、絶妙な同僚への怪訝から信頼等、様々な愛が描かれる。
人工親友として生まれてきた宿命や価値観は揺るがない。そしてきっと最後の扱いに関しても、双方や社会的な価値観としての役割と処理の仕方は確立されているのだと思う。クララも知識として、子供の成長の段階によって離れる存在だということを知っているのかもしれないし、ジョジ―がそれを当り前のようにしていることからも、世界観としてそれは常識なのだろう。
別れを感じてからの地の文だけでもわかる健気さ、別れの近さには、こちらの同情を買う可愛らしさがある。そのいじらしさ等から際立つクララからジョジ―へのまっすぐな愛、そして全編に渡るお日さまへの絶対的な敬愛。
自分の生まれや存在に疑いを持たずに、尽くすことが幸せだし役割なのだと絶対的に信じられるクララの純粋さは、そのまま本作で唯一といっていいほどの不穏を持たない温かな安心であり、クララが語る物語の真価そのものである。自我がないからこそ、その愛は、自我である人間には無理な純粋であり、これこそが本作の寓話性の達成の肝で、人称を使いきって作り上げる本作の真骨頂だろう。
クララがまっすぐと信じた愛の達成を勿論クララもその胸の内に温かく宿しているが、それをクララに対して持ち得てくれた人はいるかと思えば、「クララにそんな不当な扱いは許さない」と二度もかばってくれたジョジーの母親リクシーが思われる。母親にとっての自我は自身から子供にすり替わり、クララに対するその芽生えは一瞬でもジョジーを重ねた疑似的な愛であり、錯乱の中に生まれた妄信的な感情ではあるが、それらの愛はクララのお日さまへの愛にも似る。そしてもしかすれば妄信的な愛と勘違いの作為は、クララからジョジ―への価値観にも該当する。クララは自分のまっすぐさには言及しないし、自分が捨て置かれる最後にも感情的にはならない。その意味で本作は温かさとは全く逆の、信じる者の悲しみの物語であったともいえるのかもしれない。
愛を知らない残酷な子供に愛を教えることは友達にはできないし、愛を知る純粋な子供に君の不幸を教えてあげることもできない。だからどんな交流会を持ってしても子供だけの矮小な世界でのやり取りに、彼らの人間性を育む答えは生まないかもしれないし、子供たちに買い与えられたAFがどんな扱いをされようとそれは受け入れる運命であり、曝される毎日あり、そのようにしか生まれなかったクララの命は自身に問われることもなく閉じていく。
囚われた人称で生きていく私たちの自我は、自分の意思決定に客観性も妥当性も持てない。愛と寓話に溢れた物語の内側にあるものが、どんなに厚く魅力的な子供の世界を描けたのだとしても、その到達点は結局のところ子供時代に収まる。クララによる寓話性の中に収まる本作のテーマは、等身大のクララの内側に閉じていく。
かつて私がカズオ・イシグロに感じた軽薄さの正体は、彼が書かない部分にある書けない部分であり、それを私が文学に求めているからではないか、と私はまだ疑っているが、本作はその寓話性と子供の背丈の人称設定により、創作的な魅力と達成を模しているので面白く読めた。
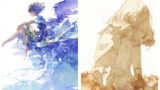
おひさまのランキング登山、こつこつ
登頂まで応援よろしくお願いします🌞
⬇️1日1クリックまで🙇♀️☀️
小説ランキング












コメント