人類と文学の祈りが切り離せないように、人類と金融経済も切り離せない。その交わるところにある作品こそ、個人的な主題になってもおかしくはないのか、とふと気づいた本作の読書観。
フルタイム労働の間にsnsデビューした私の長らくの主戦場は金融投資を話題にしたアカウントでしたが、その後セミリタイア中に復活した読書趣味を報告する当ブログを開設。その両方の交わるところにある本作品や、かつて扱った金融関連の映画など、実は虚構創作的にも現代人類的にも、文学性と共に金融経済は必ず存在し並走している。
人類の発展と世界経済の右肩上がりを願う私は、常にその虚構性と憧憬を求め続ける。



「文芸×金融」モチーフ作品を、さてどう書けるか
2025年最初の佐藤亜紀作品は18世紀初頭のパリを舞台に、三大金融バブルとも数えられるミシシッピ事件(1720年フランスのパリで起ったアメリカ植民会社にまつわる金融投機破綻)を題材に、可愛らしく分かり易い童話的なキャラクター人形劇とそのト書きのような文章。
佐藤亜紀作品は初めてだし普段小説は読まないけど株式や金融には少し強いわ、という人には非常にお勧めできるし、私のように文芸を舐めた読者にもいくらでも深く楽しむ要素があることに気づく読書の魅力もあります。装丁もいい、本作は売り方や勧め方を間違えなければいくらでも売れるし読まれる作品、埋もれていたことが勿体なく感じる私はさてどう書けるでしょう。
ハードカバーの装丁可愛いけど絶版?文庫なし?売る気無し!電子書籍なら500円で読めます
『金の仔牛』あらすじ、概要
道行く人を狙って追剥をしていた青年アルノ―は、ある夜襲った馬車の中で老人カトルメールが雨宿りの間に語る金融の小話を聞く。その理解から世界が一変し、可愛く愛しいニコルと出会い、元追剥風情に娘をやりたくない父親との確執にも気づかず求婚をし続ける。若く美しいニコルを伴った社交界デビューと賭博と華々しい成り上がり生活、うなぎのぼりの株価と阿呆の才覚、いつ弾けて転ぶ投機と世相なのかとの不安と、家庭用ギロチンを持つ敵役への慄き、追剥文化の大物を相対において暴力的な恐怖は和らぐが戦局は増え、個性豊かな三人と友人と思いやりと策略、一筋縄ではいかないニコルの父親との幾度にも渡る折り合いの悪さ、そしてピストル。
1719~1721年の歴史上で、スコットランドの実業家ジョン・ローが巧みなマーケティング戦略を用いて熱狂的な投機買いを起こし、ミシシッピ会社の株価を500リーブルから1万リーブルまで高騰させた事件を本作でもおおきなプロットで明確に採用。人々や買筋を熱狂させた二年間とその後の幕引きについては本作上のネタバレでもあるので控えるとして。
多彩な佐藤亜紀の真骨頂とは?
一般的にとっつきづらく分かりづらい無機質な金融をテーマモチーフに、それを読みやすいようにおとぎ話的ディズニー的に作った感じにまず意外性があり、『喜べ、幸いなる魂よ』(2022)を読んだ時に感じた意外性は、2012年出版の本作を読んでいたら感じなかったかもしれない。
本作が画期的なのは、古典的な虚構性モチーフを扱っておとぎ話風に面白く書ける正統派の作家性、というところ。私がびっくりしたのは、個人的には『ミノタウロス』や『黄金列車』の重さや威力が佐藤亜紀の真骨頂だと認識していたからこそ『喜べ、幸いなる魂よ』の明るさ軽さに驚いたけど、よく考えたら初期作からの変化で考えれば、佐藤亜紀の本質は文化を鼻で笑い形式も笑いながら上品さを気取る本気を出さない煙に巻いたようなけだるさと皮肉にあるし、けれどその本質の初期から徐々に創作や出版に向き合った結果、明るくもキャッチ―にも書けるということの証明と、ある意味で本格への脱皮ないし納得までの融合であり、つまりその創作性、と見て取ることも出来た。それらが近年、著作列の後半に来ていることはとても好感触で素晴らしいし、作風の革新や変貌はさすがとしか言えない、しかもそれが佐藤亜紀的には受け付けない感じがする正統派なのだから。
ある意味で本作はその途中にあり、おとぎ話的本作の明るさ可愛らしさ軽さを物にしてからの、『喜べ、幸いなる魂よ』は必然の明るさで、著作列順に読む素直な読者にはそれほどの驚きはなかったように思えるし、処女作は中間的な趣があるが、『戦争の法』『雲雀』『天使』はその変化球、SF性とか先鋭性とかの時代的な要素があったように思うし、題名から察するに未読ではあるが『モンティニーの伯爵』『吸血鬼』、『醜聞の作法』や本作などが洒脱で煙に巻いたような作風だったのかなと推測。


著作列で振り返る佐藤亜紀と本作の読み方
(1991)『バルタザールの遍歴』 既読
(1992)『戦争の法』 既読
(1993)『鏡の影』 既読
(1995)『モンティニーの狼男爵』
(1997)『1809 ナポレオン暗殺』
(2002)『天使』 既読
(2004)『雲雀』 既読
(2007)『ミノタウロス』 既読
(2009)『激しく、速やかな死』
(2010)『醜聞の作法』 既読
(2012)『金の仔牛』 初読
(2016)『吸血鬼』
(2017)『スウィングしなけりゃ意味がない』
(2019)『黄金列車』 既読
(2022)『喜べ、幸いなる魂よ』 既読
順番で言えば『ミノタウロス』『バルタザールの遍歴』『鏡の影』『天使』『雲雀』『醜聞の作法』まで読んで、自分の読書の中断よりも前に打ち止めになっていたのは、『醜聞の作法』が個人的にはあまり響かず、著者特有の本気ではない構えみたいな要素が個人的には少し微妙に感じ、どうしても『ミノタウロス』路線の威力が忘れられなかったから。実力には感動したけれど、その志向性は相性が良いとは思わない気持ちはあった。
本作もまた、虚構性も分かり易いし文章も軽くて読みやすい採用の反面、そのように書いてあるから文章から生まれるはずの表現的な厚みはない為に文芸ベースの味わいや威力には欠けてしまうし、軽やかな上品さのみで思考性や主題性が強くないのを良しとする感じに物足りなさがあった。さらに、ここまで虚構モチーフ的に集めた強さに対し、盛り上がりや起承転結のエンタメまではしてない創作性に関しても『醜聞の作法』と似た印象、佳作という感じ、ある意味18世紀的な上品さの中にあるまろやかさが味で、上品さをまとってどこにも置いて来る志向を感じないというか、ある意味それは個人的には逃げだと思っていて、虚構創作としても主題テーマとしても渾身を逃げている、貴族的というか、個性や志向性だとは頭ではわかるのだが、私はそこはあまり好きではなかった。
このあたりのプロット上の硬さや文章の重みといったものに関して、読書再開後でブログ開設後に読んだ『黄金列車』『喜べ、幸いなる魂よ』は二作とも洒脱に構えても煙に巻く作品でもなかったことが好感触に繋がって、本当に初期の要素を忘れてしまっていたことを今回思い出す。
ただ、本作がまず明確に評価できるのは、テーマモチーフが一般的には読みづらい金融であるからこそ、読みやすくする工夫はそれだけで高価値だし、多くの読者に勧めやすく楽しみやすい読みやすさはそれだけで良点、金融題材をディズニー的な記号創作をするという様式美や創作性はやはり正統性。そしてそのシンプルな読み心地やある意味で商業性を佐藤亜紀が採用するのがまず意外だったし、中盤まで純粋に楽しく読める。
マネー・ゲーム、株式市場や金融の昔話や基礎、敵と味方と三つ子と双璧と親心と男のプライド渦巻く、殺し合い騙し合いひしめき合う世界にあって、追剥ぎ相手の老人をきっかけにあれよあれよと新しい世界に引き込まれる主人公は、可愛いヒロインとも序盤で落ち合い、義理の父親とのひと悶着やその妻には肝っ玉、極悪なキャッチ―敵役のハラハラ、それと相対的な野党グループの長、なによりダンブルドア的な強力で絶対的な味方、けれどそこは株式や投機の世界、けれど馬鹿ではないヒロインの才覚と愛らしさのカップルは癒し。
プロット運びとラストも良く、才能や役者を周りが放っておかないことに加えて物語を落着させる意味でのオルノーの呼び戻しまでの丁寧なつくりをさらっと書くところも、世界を覆う金融の支配や有機性を知らなかった頃にも戻れないことも示唆する含蓄の豊かな場面で、行く先にはカトルメールの次なるロンドンが自然と浮かぶ。
ふと悟って足を洗う場面は悪くないし、その後引き戻されるドラマの作り方も滑らか、ただそれ以後の金融の崩落的な場面の盛り上がりは表現や頁数的にも欠けるし、結局は一番の敵となる義理父親との決着の場面における彼の凄みがそこまででもないから肝っ玉義母の「惚れ直した」が響かない、ここの虚構性が微妙。結果的にそこが本作のプロット的な山場だからこそ本作の弱点だと感じたが、私はオペラや戯曲性に強くないので、これはこれで様式美なんだろうかと、ふと疑問に思う。
本作で採用された虚構性はエンタメ性ではなく、あくまで中世的な童話風の様式美であるとすれば、私が感じたディズニー的興味や期待はウォルトディズニーが巨大に吸い込みながら作り上げてきたエンタメ帝国の虚像に操作されていて、佐藤亜紀が本作で採用した18世紀的なおとぎ話はその一部に過ぎず、私の期待が見当違いであっただけかもしれないし、私も創作性やエンタメや商業性を最大価値に上げ過ぎであり、派手であればそれが至高でもないし、情動や見栄えだけがドラマでもないはずで、その意味で私の商業性やエンタメ虚構性に対する見識や常識の狭さ低さと考えることも出来る。このあたりはちょっと勉強不足と、狭さを感じる部分でもあった。
本作の凄みと描きたかったもの
では、それにしても金融おとぎ話の中に埋め込まれた群像や本作が描き出したものは何だったのか。
題名に着目すれば、金の仔牛というタイトルは、効果的かというとそこは個人的には微妙。偶像崇拝や拝金主義などの要素は勿論見て取れるし、政治や銀行などの上層や戦略上の思惑によって他者や社会的に翻弄する要素はテーマ的ではあるものの、本作ではそれらは採用されておらず、主題性には欠く。金の仔牛もまたドラキュラ的なポピュラーモチーフであり、その額面通りの虚構創作だったと思うが、追剥ぎ、襲う馬車、騎乗位、馬丁の少年、自分の馬車、ラストにまた追剥モチーフの過去と経験値による想定が抜き去り、無事からまたロンドンへ、と多くに絡ませた馬のモチーフのが強いし、むしろそちらが本作の個性にも繋がっている。
テンプレ的に個性豊かな登場人物たちの面々と人間臭さ、シンプルな感情面が目立つが、別に佐藤亜紀がそんなものを主眼で書きたいはずもない。
欲や怒りの感情、主人公は特別嫌なやつでもない爽やかな阿呆なのに、可愛い娘を預ける相手には不足なうえに、生業にしてきた自尊心もあるから振る舞いが許せない執念的なもの、或いは強欲から他人の金品を奪って殺して尊厳すら簡単に奪う底知れぬ欲求や悪趣味、そんな人間も同じ世界に存在する怖さ、主人公すら元追い剥ぎ、人は簡単に殺される、株券も紙幣も簡単に紙屑になる、名を上げたい、自分の仕事がしたい、お金が欲しい、良い目が見たい、それら複数の人間の複数の欲求や執念が渦巻く人間社会を、一人の人間の人生や感情やドラマに執着することなく群像としてさらりと描いたそこに底知れ無さがあるし、本作のある種の爽やかさは誰のことも執拗に描かなかったことにもよるかもしれない。
主人公カップルが代表的に爽やかなのは描き込まれていないからだし、強欲な世界を描きながら恋人以外には際立った執着をしないという体現としても、本作は彼らであるし、彼らは本作であるとも。
故に、執着している側が目立つし人間の業が目立つが、それもさらりと書いているからこそ、拝金主義、物質崇拝、唯物論、そのモチーフだとすれば、描きすぎない本作の趣向は虚構的な多数の登場人物が織りなす群像劇で、誰も明確な濃厚さで表現されはしないし、どの場面も描き尽くしてはおらず、無駄な描写は排除され、ただの記号的なおとぎ話で、情感を汲めばいくらでも膨らませることが出来る余地は読者に残され、作者が塗り固めるものではない創作性すら感じる。
語り過ぎない書き方で目立つのはむしろ、滑らかな物語の形式の抜け目なさ。最初は物足りなく感じた書き込みの弱さが、大袈裟に表現せず誰にも抑揚をつけすぎずに書く凄味は、ほとんどト書きみたいなもの。いくらでも読める、いくらでも楽しめる、そしてモチーフは歴史的金融事件、この読みやすいシンプルさは無駄のなさで肉付けは読者に委ねられており、斜に構えたイメージのある著者は読者のことなんて信用していないだろうが、こういうものを書ける。素晴らしい確信だと思う、私には無い。
小説ランキング

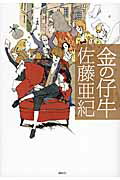
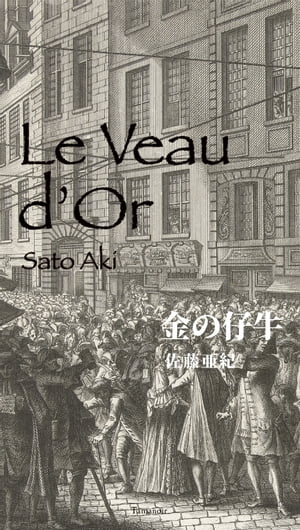


コメント