構造の中の声の純度として最高傑作が芥川賞を受賞しつつ、その潮流の継続を果たし、以降にも影響を与えたことから2000~2020年代を語るうえで避けて通れない一人として、今回は待ちに待った絲山秋子さん。
20歳前後まで読書をしていた時期に、デビュー作『イッツ・オンリー・トーク』と川端康成文学賞『袋小路の男』を読んで、当時の私は今よりも、海外作品が好きで日本人作家の作品の狭さに落胆する青さがあったりして、なぜ彼女が恋愛小説風味を書いているのか、なのにどこか強度があって他の作家と何かが違うと感じながらも、それ以上の詮索はせずに離れてしまいました。
芥川賞企画をするときに、再びその著者名を見つけて歓喜、この人を読みたくて芥川賞企画を進めてきたとも思えます。今回は、芥川賞受賞作『沖で待つ』代表作の強度密度、会社員小説繋がりとタイトルのキャッチ―さから『御社のチャラ男』、装丁の鋭さから絶対読みたかった『ニート』、文藝賞を受賞したデビュー作『イッツ・オンリー・トーク』を再読。
特に代表作で受賞作の「沖で待つ」と収録作「勤労感謝の日」の2編は、20歳前後の私が読んでいてもここまで響かなかっただろうし、その凄味が分かったとも思えない。今だから読める、書けることの喜びを感じた一冊。
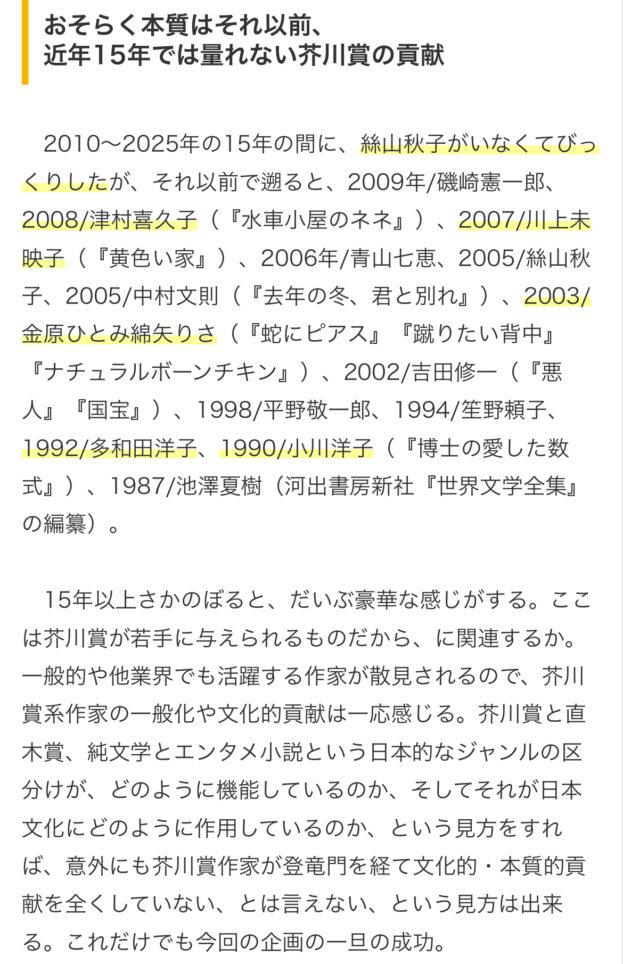
**モチベ・やる気アップします**
ご訪問、拍手、感想、経由購入、全部力になります🌞

綿矢金原が奪還した語りの主体
少女性から中年性へ進む絲山秋子
前回のおさらいとしては、平成の大事件として2003年の綿矢金原の同時受賞により、メディア的爆発や商業利用の片側に本質的な文学的貢献として、語られる側だった少女たちが自らの言葉で語り始めることにより、自己の内面としての身体や感情が少女自身の声として初めて語られたのではないか、という部分から、語りの主体の奪還を感じ、これは日本文学の一つの転換期と捉えて間違いない、と私には思えた。若年天才看板や同時受賞の華々しい話題性の裏に、彼女たちは「少女」が文学の中で観察される存在から世界を観察し語る存在へと転換した、戦後によくある弱者男性文学に登場する描写される少女としてではなく、自分の身体や感性で語る言葉により、語り手の権力移動を成功させた。そしてそこに国内特有の「少女性」への商業価値も重なって大爆発し、以降の雑多な潮流を生む。
それを引き継ぐ形の2年後の2005年に芥川賞を受賞した絲山秋子は、では何を更新したのか?
2007年に受賞した川上が20代後半から30歳前後の、少女から大人への転換期の身体と文体のリズムで独自性を築いたことは、すでにブログ記事にもしている。この並びを見ると正統派の並びが見えて面白いのだけど、ただ実は川上より3年早い2005年に絲山は30~40代という年齢の女性の語りを開放したし、2003年綿谷/2005年絲山/2007年川上と見ると、いかに絲山が成熟した文体を持つかも圧倒的だし、加えて性別も年齢も関係ない構造性にまで伸びる作風を見せつけた感がある。



更新した文学性
絲山秋子の解放した中年女性の声や会社員小説としては、「沖で待つ」や「勤労感謝の日」に代表する、男女雇用均等法や女性総合職のワードと共に昭和の時代を生き抜いた働く女性が2005年の芥川賞受賞で顕在化し、昭和から平成にかけての働いた女性の辛苦と年齢と独身で表す一端が一つと、『ニート』『御社のチャラ男』に代表する、会社や労働を構造にした場合の個人を描く社会性の2パターンがあり、 前者は文体による開放で、後者は構造による描写、どちらも著者の文学性ではあるが、関わり合いながらも別次元のものだ。
絲山秋子の二つの革新軸を「①文体による解放」「②構造による批評」としてみれば、著者の文学はモチーフ的には会社員小説や独身女性の声としてまとめられがちかもしれないが、この両点には異なる2つの文学的アプローチが併存している。
1| 女性の主体性の更新(中年の解放)
綿矢金原の時点で少女自身が語ることは無画期的であったとして、さらに中年女性として30代~40代女性の壊れかけの主体を、内側から書く前例もまたすくなかった。絲山秋子は、少女文学でも男性的私小説でもない、壊れかけた大人の女性の流れる意識を文学化したといえる。
語られ描写される対象だった少女たちが内側から自分たちの言葉で語り始めた綿矢金原に対し、語られることも描写されることもなく存在することも見つめられなかった中年女性の語りは、ともすれば前時代的には昭和や社会の中の弱者要素もあるが、確実に存在する女性像である。令和になった現時代的にも確実に存在し、自分の足と知性で社会の中で生きている、妻にも母にもなってない女の叫びは、弱者・強者・自己満足・社会貢献、多くの萌え芽であり、新しさであり古さである。
2000年代はネット時代的にもまだ前夜、その先取りをした世代の綿矢がsnsやネット時代の前衛として書いたが、2025年の現在は時代も経過してsnsにおける内面の吐露は珍しくもない為、例えばすぐ思い出すのは「割と綺麗な社会のゴミ」さんなどsnsに溢れるあらゆる年代や階層の女性の存在の価値化や顕在化が為されたが、その前夜における主体性は絲山のあたりにあったのかなと。もっと器用なら、自分を曲げたり負けたり諦めたら、社会の型にはまれば、男性であったならば、もっと簡単に生きられた、手に入ったものも、不器用に生きた結果の意味では弱者なんだけど、それでも諸々に晒されながら一人で生きている強さなどなど。
これは今後ももっと加速するし、その時の憧憬やロールモデル性は確実に価値性であり、希望、つまりは文性になり得る。母でも妻でもない女性に価値を与えることは、人類普遍的な要素を水平線に持ってくることであるし、相対的には母や妻になって諦めた女たちの憧憬ですらあるし、それらはすべて性別に縛られない生き方の多様性のパターンを提示していく。
勿論かくいう私すら、絲山世代(50代後半)からすれば若いし弱者であり、ある時代は未経験であり今後を生きていく現代の今ここの人たち、どの時代のどの世代の女性が、どれだけの強さと弱さで、どれだけの価値で輝き貫いて今を生き、過去を生き抜いてきたのか、その女性・独身中年女性、その語りの解放は、間違いなくジェンダーだし文芸。

従来的な意味での孤独や独身には痛みや透明化があったし、従来的に女性は従属の非主体性として描かれたり、「癒し・憐さ」に依存した感情美学で描き、女性という主体は依然として受動的であったし、どのように何をして社会の中で生きているのかは不明なまま、女性作家ですらその具現化にはたどりつけなかった。前時代的なイメージのある川上弘美・吉本ばなななども純文学性とか言われるとよくわからないし取るにならないものだと個人的に感じるのにもそういう部分が関連するのだと思うが、絲山にその雰囲気はない。
代表作に感じるところの、「独身/年齢化(中年化)/働き続ける身体」「男女雇用均等法をくぐり抜けた世代の女性」その痛みや孤独を哀しみではなく主体や主権として描くことであり、重要なのは、女性の痛みや透明化されていた存在を語りの主体として転換したこと。
2000年代に、綿矢金原が扶養される少女の側から主張を始め、川上未映子が身体と言語の衝突により痛みや苦しみを表現したが、恋愛・身体性中心の閉域性は残り、社会や労働との接続はまだ薄いまま、古典性を継続。絲山秋子の登場により、中年女性の位置取りを獲得し、「養われていない/媚びない/泣かない」などの要素を含めて、なんなら「養う/殴る(死なせる)/泣かせる」ですらある。働くことによる生活や人生を引き受け、母でも妻でもない孤独は敗北ではなく姿勢として描かれ、その内的な悲しみや叫びよりも、その社会的立ち位置や成り立ちで描かれ、結婚していなくても、若くなくても、「私は私としてここに立つ」と言える声が、家父長制や男尊女卑が強めな戦後昭和の文化や文学の中では見つからず、その虚構創作の無さは文化に響き、恐らく絲山で初めて中年女性の誇りや生き方が文体になったのかなと。
となると勿論、それ以降は中年女性の主体の多様化が文学にも表れるし一般社会的にも普及していく。その時代の普遍性を描き出すことに成功し、その表現が文化や文学的祈りとして浸透する。
「かわいそう」でも「痛々しい」でもなく「自分で立つ」中年女性が初めて文学の主人公になったし、絲山が道を通したので、他者が現実的にその道を歩けるようになった。これは文芸のみならず、文化・社会・ジェンダー、多くの面で一つの契機となる。
そしてこれらの文体や虚構創作は時代と共にさらに隆盛する、その意味でも女性作家やジェンダー文学は今後もっと伸びしろがあるし、それは日本的な女性から韓国人女性的などのパターンで全世界的に存在し、当時代的な社会的出来事の勢いやパワーが確実に文学や文化を後押し、うねりながら人類社会化が進む。このあたりのことはまた。
つまりはそこを嗅ぎ分け書き上げるに至る著者の半生の価値と共に、そこから始まる時代感覚が絲山にはあった。
綿矢金原が更新した少女の主体性の奪還/少女性への商業性強さを引き継ぎながら、中年女性や独身女性の透明化からの回復的転換が続くし、そのようにして構造や社会性に消費される少女性から、構造の中を生きる一人を浮かび上がらせ、かつ社会構造的批評まで加えて展開しているところに絲山の凄みを感じる。
絲山は基本的に情動物語を描かず、中年女性を描きながらも基本的な主軸は構造側にある。これは以下②にも繋がるし、感情を被害の物語に閉じ込めずに自分の距離を保ち、誇りを持ち、生存戦略として語り直す所の強さがその真骨頂となるし、そのように語られることで浮かび上がった「中年女性・独身女性」が生きた昭和であったり当時の会社や社会というものが自然と立ち上る、ここの文学性が素晴らしかったし、上記の2作は『沖で待つ』に両方とも収録されており、ここの純度が素晴らしかった。
著者は個人のドラマには興味がないし、それでもこの2作は著者の経歴や年恰好を思わせる人物造形をなぞっており、この声の純度は勿論著者だから書けたドラマとして輝くが、それもまた情動ドラマの心酔や自己憐憫に陥らずに、あくまで個体の主体的な声を保っているところが素晴らしいし、それが表す再現性や普遍性に価値がある。それにしてもそれを引きずらずに、以降はあえて構造の中の個人を描き続ける、その姿勢がまた良い。以降の構造とは②へ続く。
安い言い方をすれば、ある意味で恐らく絲山は「働く女性の美学」を日本で初めて確立した作家と言えるだろうし、かつそれを身を以って人生ドラマとして半生を働いて生き切った血肉の上でこの作品を上梓した、その価値や苦しみが分かる年齢や労働との向き合い方を私がしたことがあるし、時代的には今もその渦中である、ということにあるし、そんな私の軽薄で若輩な時代と社会人経験とは全く異なる次元と時代を生きた著者の、他階層からは想像し得ない厚みを文芸によって垣間見ることが出来る、これが文学性以外の何なのかと思う次第。
おそらくこの「労働・時代と会社・中年年齢・単身女性」の要素は、現代的かつ今後さらに普遍化するものであり、その先人や虚構作品化が済んでいるということが、普遍的な社会人女性や文芸として作家として書いていく後輩にとって、どんな価値があるのかを含めて考慮すればこの効果は大きい。綿矢金原が始めて絲山が展開し、川上が受けて、さらにいろいろを含んで宇佐見やほかにも届いて、紡がれ続けていく大事な価値の系譜を思わせる。
個人的には全く価値を感じないまで言えるが、多く哀しみの系譜としての中年女性の孤独や生活なんかは、(吉本ばなな・川上弘美・角田光代)などの当たりは書いて来たのだと思うが、癒しではなく主体の自律へ繋げていく更新の強さが、近代的な普遍性を持っていく。
勿論その「自分を養う・母でも妻でもない」女性像が理想的や正統派だとは言わず、成熟しきれなかった中途半端な大人の女性として登場もし、議論にもなるだろうし、「主体の崩壊・回復・破片化」をリアルタイムの文体として書いた、という部分の屈折や不条理の祈りが、むしろ決定的な新領域であり、かつ古典的な純文学の狭さと熱さにも合致した。
会社・社会・男女関係・家族の中で晒され続けた壊れかけの主体のプロセスや叫びでもあり、弱者文学的つまりは純文学的であるし、新しい女性像を文学的表象的にアップデートした、という見方も出来るのかなと。少女には書けない、男性作家にも書けない、中年女性の内側からだから書けたものを、文才や批評性を持った著者が書いたことにも意義が生まれていく。
恋愛的に勝ちやすくもない、商業的に少女よりも簡単に売れない、強くなりくたびれて愛想笑いもしなくなる、少女を脱したあとの傷ついた主体の継続をどう語れるかの文学形式として、中年女性の意識を顕在化させた。透明だった苦しみも、そこにある喜びや誇りも、明確な密度にしてみせた。そしてそれは自分が生きた時代、同じ時代に少女として成長していく世代、今まさに中年女性の暗がりに響く。
文体や語りについて言えば、結局は小説は文芸形式の作品表現なので、文体や文章が作品の威力に直結するので、その部分でさえ抜かりなく十二分に機能するのも強い。
絲山秋子は「独身・年齢化(中年化)・働き続ける身体」の痛みや孤独を苦しさやユーモアで同じ温度で書く。生活の疲労、意識の断片、どうでもいいことの反復、そのすべてが語りを構成する材料になり、壊れ続ける意識の主体を日本語でどう書けるかを体現していく。
日本語の小説には伝統的に、三人称的な地の文と、語り手=作者の知性が全体を統制する趣があったが、絲山の文体は感情の揺れがそのまま文のリズムになり、言い換えや言い直しがそのまま残り、思考の寸断や落差が文体の構造になるなど、語り手が一定の統制を持たない文体だとのことで、日本語の地の文の権威を破壊・変形した語りは構文の革命的でもあるそうで、その意味でも完全に新しく、構造批評と文芸形式における文体の、ミクロ・マクロ両面から強いのが絲山なのかなと。
( アメリカ文学で言えばリディア・デイヴィス的、フランス文学ならエルノーの手前の生の断片、に近い「崩れ方」を日本語に移植した作家。)という表現を見たけど、いまいちわからず
2|構造による批評、人間関係や労働世界を構造として描く
絲山作品では、個人や情動よりも「関係の仕組み/階層/非対称」が主役となり、多く著者の著作の主体となっているので作風や世界観や価値観と思っていい。著者が描く「会社・ニート・恋愛」が、ただの舞台や弱者の嘆きやメロドラマに終わらず、構造に始まって構造にこだますることの理由がここにある。
人物の感情は社会構造の産物であり、物語の中心は人間の自我ではなく仕組みとしての回路である。この視点は、例えば川上未映子や津村記久子の心情や身体のリズムや人物中心志向性と決定的に異なる。更に言えば、社会構造を批判するでもなく、描写によって露呈させるだけに留まる点が特異で、その批評性は構造の凄みや悲しみを描き出し、都市社会学的な味わいをもたらす。
労働小説は階級か生活を基本としていた感がある中、絲山は労働を制度として描いた。
戦後~70年代は、労働者の権利・階級闘争などの文脈で、制度は敵として分析は外部的に留まり、80~90年代の「職場」は舞台装置であり、基本的に主体は自由人として労働が補助的な装置に留まる。2000年前後にはワーキングプア・非正規などの社会現象の内的感情の物語化が主であり、それまでの労働小説はすべて感情ドラマであり、労働はつらさの背景でしかなかった。
「労働する主体」ではなく「労働によって設計される主体」を目指した感のある作風で、恋愛小説を書いたところで「恋愛する主体」ではなく「人間関係によって設計される構造」でしかない所にもこの著者の特異や価値観の一貫性が見える。
だれが悪いかで言えば誰も悪くないし、何が悪いかで言えば仕組みが悪い、といった具合。労働小説を苦しい人を描く情動文芸から、人を苦しくする仕組みを描く構造批評に移すこの視座は、社会学や制度設計論の導入であり、日本文学の労働テーマは絲山以後、情緒から構造へと進まざるを得なくなったのではないかなと思えたが、芥川賞以外の日本文芸はまだまだ読めていないので個人的な感覚に留まるけれど、他が先に表層に現れていないということに意味があり、それが結果なのかなとも思う。
痛みを生む構造と、
それでも立つ人間の位置取りを描く
①文体による解放
中年女性主体の獲得
=女性個人の物語は抵抗や存在論へ
②構造分析による批評性
=労働・社会関係の回路描写は階層や解析へ
この2点は抵抗と解析の両輪で成立していて、絲山秋子は社会問題ではなく社会構造を描いた。その意味で私は題材性や主題性をもとめがちで個人の小説ドラマには興味がないが、それでもなにかしら感じるものがあった20歳当時の私の感覚は間違いではなかったし、その時に『沖で待つ』の凄味はきっとわからなかったなということ。
ジェンダー論でも労働ルポでもない深度で立ち上がる物語は、間違いなく文学性で定義できる。川上未映子のような女性の身体性を生む文体リズムとも、津村記久子のような労働者の日常共感物語でもなく、弱者男性文学のような自己被害者化でもない。「関係の仕組み・孤立の構造・回路の断絶」を描いたことに唯一性があるのかなと。どちらも彼女の文学だが、成果は別次元で社会に到達している。その場合の著者の文学性とは、主体と世界の仕組みの2項が同時に可視化される場であり、その本質は、人間の痛みを描くのではなく、痛みを生む構造と、それでも立つ人間の位置取りを描く。これが彼女の更新であり、これは情動主体や個人内省主体の純文学にとって明確に新しく、強く、著者の唯一性なのかなと。
お仕事小説や会社員小説は数あるし、特にそれは文学よりはエンタメ的な創作によって消費されて普及したので、痛快さやメロドラマ性のない絲山の構造性は、その形式的静けさで勿論目立つ表現ではない。綿矢金原の少女性は商売になっても、絲山の中年性は商売にはならないし、その開放によって旧時代的な男女社会や年齢立場の幾多階層などからも反発や抵抗を持たれることもあり、社会的にも文壇的にも大きな大事件ではないが、2000年代の芥川賞の核心をしっかり受け継いで展開させた突破なのは間違いないと思う。
従来的な文学要素としての心理・告白・感情でなく、人と人のあいだの構造を描くことで「働けない人・他者と結びつけない人・主体の不全」などの弱さの実情をメロドラマではなく構造の機能不全として描くことで昇華し、内面から関係の構造へ文学の焦点を移すことで、「労働・距離・関係の不一致」などの現代性の核心を文学に持ち込んだ。その高密度が代表作の「沖で待つ」に他ならないし、そこに連なる他作品もそれを補強し、さらには「ジェンダーと労働・関係の非対称性」なども主題化し、弱者男性文学や働く女性文学などの要素も先取りしつつ不動の強さへ昇華している感もあるのも当時代性。時代における弱者を描いている文学ではあるものの、自己憐憫的でもなく恋愛小説的に描きながらも、心理情動に特化しない感の強さは他に類を見ない。
その作品に露出した構造を把握してしまう知性や批評性は間違いなく、文体や虚構性も強く、そこにある主題は温かく個人レベルまで視座を下げつつも、「主体・構造・位置取り・関係の非対称性」の俯瞰も忘れず、それを主体として描き切るところに隙の無さを感じる。
女性内面文学でも会社員小説でもない
人間関係は対称性を持たない。好きの量も、責任の質も、沈黙の深さも均等ではない。絲山はこの不均衡や非対称性を徹底して描き、しかもそれを情緒ではなく文体の切断と間で表現する。それはつまり、自己と他者、そして個人と社会の接続や相互関連の不可能性を前提に書くということであり、彼女の登場人物たちは常に他者や社会と構造的につながれない。この距離の固定性を描く作風は、語りの主体の脆さを抱えた現代社会の構造を描くリアリズムに沿っている。
「弱く・揺れ・ずれ続ける」主体こそが、現代日本文学における重要な転換点であることは、それでも生きる現代のダイナミズムと、構造を見ながら個人を思うことが続く熱さに関連するし、ここに文学性と純文学性の融合もあるように思える。だからこそ絲山は内省と社会性の交差する点であり、対人関係の構造分析を文学化し展開した突破に読めるが、他がそこに強烈に追随したかはまだ不明。
絲山秋子は2000~2020年の国内文学において、語りの主体を解放し、更新しながら書いた作家の一人であり、主体の生きる構造社会は確実に私の主題であるし、読書における内的個人と社会的構造と節点にも関わる。
絲山は、人間の「位置のズレ」「対称性が崩れた関係」そのものを物語にし、その構造や、現代の中に生きる個人の叫びや愛情は現代社会性であり、私が好む部分としても自身が扱っている概念としての構造や批評性が重なるのかなと。
以下、代表作と思しき著作の総括。
『沖で待つ』 → 距離・非対称・死の構造
『イッツ・オンリー・トーク』→ 関係線の発明
『ニート』 → 社会からの脱接続
『御社のチャラ男』→ 労働世界の階層構造
4つともテーマは違うが、すべてに共通しているのは構造の文学をやったこと。
その新規性や強靭さは上で述べてきた通り。
特に難しく考えなくても文章も読みやすいし恋愛風味によって虚構性も強いし、川上のように男性読者を置き去りにすることもなく、綿矢のような若年の未発達を感じさせる物足りなさもなく、多く読みやすいので、ぜひ気になった1冊からお読みいただけますように。
『沖で待つ』(2006) 最高到達点と半生のドラマ
芥川賞作「沖で待つ」と「勤労感謝の日」を収録。
会社員として生きた数年、新卒から新天地に赴任してからの同僚との仕事や関係や人生を駆け抜けていく。ある日にふと一つの命が亡くなる、その人との約束、友達とも恋人とも、先輩とも後輩とも違う、その命が失われた時のもう今後得難い私。
基本的に虚構創作される対人関係上のジャンルは友達や恋人や家族だったりして、愛でも友情でも割り切れない関係の言語化や認識はなかなされないが、本作はその構造分析をもとに、その二人と関係を育んだ会社員人生を浮かび上がらせた青春小説ともいえる。
恋愛でも友情でもない関係を描きながら、関係を生む構造の方が感情より強いという事実を浮かび上がらせるのは見事。唐突な死がもたらすものや、勿論奪うもの、一種の種明かしの明るさと、タイトルの響き、死や思い出の再配置の物語は、勿論関係の断絶構造でもあるし、構築した構造の強さでもある。
名付け不可能な関係の強度はそれだけで文学的だが、それはそれを描く言語化の価値によるし、その難易度も指す。その密度がこれでもかと感じるのは、表題作で芥川賞受賞作の「沖で待つ」よりもさらにある意味で密度的な「勤労感謝の日」が先に置かれていることにより補足されていて、この二作だけ読んでもなにかしら著者の中心に触れた気がして嬉しかった。
男性中心の労働世界の中の女性の位置や時代を生きた中年の思いや人生と叫びが2作を貫くし、昭和のその特徴的な時代を生きた者の叫びは、そのまま文学性と言って差支えがすでに何もない所。
このあたりの魅力を、恐らく20歳前後の私が読んでも何も思うところがなかっただろうこと、著者が描きたいもの、書き上げられたものを大きかった。
『ニート』(2005) 社会システムと非接続の主体
2000年代前半は「ニート=問題/弱者/社会不適応」がデフォルトかつ社会問題だった中、本作は 価値判断を一度外すことで再構築的な姿勢をもち、本作には劣等感も生存戦略も出てこない。
この作品が優れているのは、「ニート」を怠惰な個人ではなく社会構造の外に滑落した主体として描いた点であり、「ニート」というワードが社会問題化し始めた直後に、情緒化せず、批判もせず、主体の脱社会化として、社会規範に”適応できない人”としてではなく”接続しない主体”を描いたことにより、弱者男性文学でも社会派小説でもない、構造そのものとして2005年に早々にさっそうと描き切っているところにある。
絲山は意識的に会社員小説要素を持っているが、同時に精神病院やうつ病や休職などの要素や、それらも著者の経歴にもあるので、会社や社会の構造の中に生きることやその中で脱接続した人間についての目線も忘れない。労働とは他者や社会との接続の仕方であり、賃金や生活主体という捉え方は著作の中ではされていない。
だから本作における”ニート”は社会的役割がないというより、どの位置にも所属できず機能しない主体として描かれるし、通常であればその境遇の内面の苦しみや憐憫に寄せるだろう所を、著者はそのようには書かない。
構造からの排除であったり、他者との接点や再接続を、果たすようで果たさないし、求めているようで求めていかないし、主体と社会構造のずれを描きながら、恋愛小説風味を被せる。
社会からずれる主体の倫理から見れば、勿論逃げと責任も描いているようなきはするが、労働倫理から外れた存在を表層的に扱わず、「労働/社会の物差しでは測れない人間の生存」として位置づけつつ、おそらく絲山はだめ男好きだし、他者との関係、優位性、慰めでもあるし、主人公もかつてはニートをして現ニートに助けられていた時期があったり、これから先いつ自分も働けなく稼げなくなるかもわからない社会性と非社会性が混然としている点も注目だし、語り手は社会規範を信じ切れないし、社会に参加しながら、どこかで拒む。
「怠惰・自己責任・社会不適応」といった道徳化されたラベルとして語られがちなニート自身の、自分が社会に受け入れられない的な自意識の痛みが中核に置かれそうなモチーフであるが、本作では痛みすら扱われない点で明らかに著者が内的情緒に興味がなく、構造分析にあること、或いはそうした主体と構造の関係にあることなどが感じられる。社会に受け入れられない「私」に問題はなく、社会と接続する線そのものが切断されている「構造」を描く。これが弱者男性文学との決定的な差。
社会学でいう脱社会化(desocialization)/脱接続(decoupling)であり、著者のどの作品にも「距離・非対称・接続」といった構造ワード”が基底にあるが、
『ニート』はそのモチーフ故にそれが最も研ぎ澄まされている。本作では「職場・家族・友人関係」いずれも機能していないし、機能していない理由を心理に求めない。対人関係ではなく関係と仕組み、孤独感情ではなく孤立構造、主観ではなく社会システムの認知を描く。
太宰的な要素が何も無いのが、私には良いのかもだし、弱者男性感とはやはり一線を画す。

『御社のチャラ男』(2020) 社会構造と会社員ラベル
労働世界の構造を多様な人物視点で立体的に描き出す本作で、例えば津村記久子も同じく労働小説なようなものを書くが、絲山は階層がまったく違うことがはっきりとわかる。
労働によって再生産される人間関係の非対称性であり、社内、社外にある様々なずれを可視化していく。タイトルはチャラいが、この場合の「チャラ男」は「軟派者」の意味で使われ、単語の持つイメージは現代的とは言えないが、労働や会社の中におけるチャラ男の存在は具体的。ある一人の人物を中心に据えつつ展開することで、さまざまな階層構造を描いていくし、そのチャラ男のラベルやレッテルすら他者・起業・社会に押し付けられた主体のゆがみや不惑であるのかなと。そのあたりのことは、例えば一口に「中年女性」の主体を外側から決めて定め、「少女」たちを外側から眺めて決めつけることとも変わりないし、「ニート」「精神病患者」等の解放にも重なる。それらもたとえば、社会的演技による損得や防衛本能だったりするように、本作は「チャラ男」の裏側の孤独や責務を透かし見ていく。
つまり本作で絲山は、男性の社会的役割や機能不全を描くことをしたし、労働社会や会社内における普遍的な個人を扱ったのかなと。家父長制も企業戦士モデルも機能しなくなった男性、とすれば弱者男性文学にも接続するように思える、構造上の男性性の劣化であるのかなと。
ここでのチャラ男の軟派は人格ではなく、会社という構造に適合しないロールの歪みとして描かれ、対軸に置かれた「シカ男」の結局軟派さも目立った。
ただ若干言えば、本作は2020年の作品だが、内情や醸される雰囲気、やはりチャラ男の言語選択を含めて、時代が少し前かなと思えたのでそこは少し複雑。やはり作家がリアルタイムで体感した時代と、現代との差、或いは作品内部の時間軸など、作家の感性と才能との複雑を感じた。
恐らく読んだ限りで本作の舞台設定は明言されていなかったように思えるし、現代の会社組織が持つ世代構成として設定の違和感はなかった。
過労やメンタル不調などからの休職や世代間ギャップ等のテーマは1990年代から2000年代に顕在化した社会問題要素であり、これは現在2025年にももう少し社会的に認知されるまでに変化している体感なので、本作の舞台設定はバブル後~2010年代後半の背景に近いのかなと推定すると、チャラ男の単語イメージやそれに付随する価値観の多くが作家的感性に根付いたものなのであり、全編にわたって全年齢の視点人物が同様の「チャラ男観・言語選択」を持つ総体性は少し古さを感じるのかなと。「勤労感謝の日」「沖で待つ」は発表当時が2005年前後なので、同じ感性要素で2020年に書かれると、少しずれを感じてしまうし、その点で読み直してみると、本作はどの時代にもある社会人造や会社の病理の普遍を描こうとしているだとすれば、逆になぜ体感リアルタイムさの短い「チャラ男」という単語を当てたか、言語選択部分の違和感は残ってしまい、そのぶんで少し弱いかなと。
あと本作は私が読んだ者作品の中では唯一の長編だったが、その長さと複数の視点人物の文体の文仕方ないのだが、文章の密度としては弱いのも残念だった。本作を「沖で待つ」くらいの密度で仕上げられたらびっくりするところだったが、変化はつきものだし、色々経過を見るためにそのほか近年の他作品もまた読みたい。
ただそれにしても、構造の中の個人を日常的舞台の中で描くという分析とその描写の主体性は揺らがず、そこに浮かび上がる現代人や社会人の日常的な舞台の中に何がある故に何が起こり、どんな深さでどんな渦巻きがあるのか、を文芸で仕上げる手腕は見事。
345>会社員でいるということは、明確な役割で一つの時代を生きることなのだと、池田かな子は思う。ただ単に経済のふるまいに身を置くということではなく、もっと能動的なことだ。どの時代でも変わらないような生き方を選べる人なんてごく僅かだ。そういう資産と精神に恵まれた人は少ないし、そんな人達には私たちのことなんてわからないのだ。
本文P345
だから「どこに所属するかを選ぶ」ということは、とても大事で、そのために努力もしてきたのだ。つまり、一つの定点観測の場を持っているということだと思う。展望台とか天文台とか、そういうものがある街みたいなものだ。
業種は問わないけれど、やっぱり会社がなくなるっていうのは、自分から文化とか義理とかそういうものが奪われることに近い。子供のころから習っていたバレエをやめるとか、ずっと好きだった相撲を見るのをやめるとか、音楽を聴かなくなるとかそのくらい重要なことだ。
302>伊藤は、地獄に生きているのだなあと思う。
世の中をまず、半分に切ります(半分は敵だからです)。
それから思想でふるいにかけます。
気の合わない人を除きます。
反応が薄い人、相づちがとんちんかんな人を外します。
すると、どこからともなく、いちゃもんをつける下品な人が湧いてきます。これは個別にブロックするしかありません。
世の中を削っても削っても、吟醸酒みたいに澄んだ味は得られない。器を小さくしたって、濃縮された地獄が出現するだけだ。ほんの少し構図が変わるだけでいつまでも見飽きない地獄の万華鏡。
~たしかに俺は、男である。伊藤に比べたら頭も悪いし、考えも浅い。スケベで下品なところは、必死で隠しているがときどきボロも出る。面倒くさくて気持ち悪いかもしれない。つまり、厄介なキャラクターを背負っている。
だからと言って、人生をやり直せと言えるだろうか。彼女が正しくて俺が間違っているとしても(おそらくそうなんでしょうけどね)、「男としてこの国に生まれたならば、育ちも教育も間違っているのだから幼稚園からやり直せ」と言われているような気分になるのだ。それはつまり、言葉は丁寧だが死ねと言っているようなものだ。死なないためにすべきこと。それは、何十年分の間違いを、一瞬で理解し反省し改めることである。無茶だ。だが、その無茶に対応しないと、アップデートできない古い時代の生き物と認定されてしまう。つらい。それができないなら、死ぬまで謝り続け、贖罪の日々を送れと言われたような言われていないような。まあ極端かもしれないが。
ものすごく平たく言えば、自分が地獄に棲んでいるから、あんたも地獄に落ちなさいということ。
137>もちろん東京に行ったところで本質はなにも変わらない。「圧倒的」な才能なんて、何をやっても見つからなかった。一生つき合えるような友達はできなかった。ナンパして短期間つき合った彼女はいたけれど、本物の恋愛も経験していなかった。
つくづく報われない男だと思った。
新卒で就職した石油化学工業の会社を辞めてアメリカに行ったのはもちろん自分探しのためだ。バスでアメリカを横断しようと思ったがあまりにだるくて、すぐに西海岸に引き返した。そのうちに自分探しなんてダサいということに気がついた。こういうと三年くらい滞在したように見えるかもしれないけれど、実際にいたのは半月にも満たない。もちろん英語なんて不自由したままだ。
最後の引用は、作中のチャラ男を視点人物にした章。
チャラ男はチャラ男で自己認識をしていて、その上で生きていく、生きている事実もフラット。
『イッツ・オンリー・トーク』(2002)
10>引っ越しの朝、男に振られた。寺井という、みっともない、なんのとりえもない男だったが、私を好きだというのでぬいぐるみのように車にのせてあちこち連れまわっていた。オートマ免許だったから私の車の運転さえできなかった。二週間前に京都に旅行したときは友だちに紹介していた。私たちに公認を出したのだ。それが突然、というか、電話の線をまさに抜こうとしているところに「別れよう」ときた。ああ、いやだ、だからだめ男はいやだ、だめ男ばかり好きになる自分が嫌だ、すべてが一瞬止まりそうになったがとにかく頭を切り替えて小さなイタリアの車、うす茶色のランチア・イプシロンのエンジンをかけた。三日で四往復して引っ越しを済ませると、男のことなんかすっかり忘れてしまった。
本文P10
『御社のチャラ男』にない密度はデビュー作にはあるのだから、これはもう思考や姿勢の問題だし、作風の変化だと思うしかないのかもしれないが、もうこの序盤の文章だけで好きだし密度。
複数男性に囲まれ関わり合う構造を持つ女性を主人公に、中年女性の恋愛を描きながら、対人関係と距離の文学という手法や主題がすでに確立されているのが見えるのが良い。
「孤独・躁鬱・未婚女性(・労働)」という絲山作品のキーワードや設定も散見するけれども、基本的には、異なる距離の関係が、どのような構造的非対称を形成するか、が焦点のはずで、主人公・優子の周りには、
・借金を抱えた後輩(いとこ・間違えてもいい相手だが、養う家主との関係性は壊せない)
・マチアプ出会いの元ヤクザ(鬱仲間・追い込まれた社会的弱者)
・政治活動家 (ED・理解も出来るが、恋愛的に自分は選ばれない)
・セックスフレンド(痴漢・既婚者だが痴漢だから不倫ではない、快楽事故)
など複数の男性が登場するが、彼らは恋愛候補ではなく、関係の異なる距離として扱われる。
すべてとの関係は、接続不可能な関係だが悲劇性は描かれない。消極的な関係そのものは、時代性もあるような気がするし、無理に人と繋がらなくてはいけない理由も制度も存在し亡くなる現代も感じるし、女性の選択性も感じる。
■ ② 労働と精神疾患の接続
会社員としての経験や鬱の気配は、弱さなどの悲観ではなく。システムに持続的に構成される主体として描かれる。精神疾患などが個人の心の病ではなく社会構造が個人にかける負荷の形として扱われる部分も、『ニート』や『御社のチャラ男』にも関連する部分。
個人の弱さや現状を、個人のせいではなく社会のせいであるとした、構造の中の社会的な個人を指すし、それは昭和を生き抜いた独人女性の強さ弱さもだし、ニートも精神病院患者も含むこの場合の文学が描くのは個人の嘆きではないが、社会の中の個人の構造上の叫びであり、構造的再生産として生きるそれは、ただのメロドラマや恋愛小説に終わらない。
本作で新人文学賞を受賞したデビュー作としての位置づけにより、『イッツ・オンリー・トーク』は女性の内面文学の延長ではなく、対人・労働等の関係社会学的構造性文芸として十分成り立っており、絲山はデビュー作から徹底して関係や構造を中心に執筆していることが分かる。
複数の男性とのズレた距離や非接続を描くが、主題は恋愛でも自意識でもなく、複数の関係線が交差するとき、主体がどのように世界を認識するか。
弱者男性文学の部分でも触れたことだけど、日本における純文学がそもそも「自意識の閉塞・恋愛の情動化・生活系の縮小再生産」だったりするので矮小の中を感情的に掘る以外の手法や視点が欠落していた感があり、その狭さや謎の熱量崇拝みたいなものが気持ち悪くて私は好きではなかったが、そこへ行くと絲山作品は関係や構造への批評性で構成されていて読みやすい。そしてそれらは、「ジェンダー文学の深化・非恋愛的関係への注目・労働の社会構造化」など現代的にも一般化するテーマの先取りでもあるものを、さっそうと2000年代前半に書いていたことになる。
90年代の自意識文学も、2000年代の情動中心小説たちとも違うこの視点をデビュー作から持ち得、以後多くの作品の基礎になっているはずだし、最もシンプルな形で表現されているのかなと。
文体の解放だけでなく構造批評として、現代文学史において、避けて通れない転換点になったのではないかと思うのだが、後進が続いているのかはまだ不明。その辺りは2015~2025年の色々を読まないとわからないのかもなとも思う。
批評構造と虚構創作上の4点
(距離/関係線/脱接続/階層構造)
著者が更新した文体や主体性の後に来る著者の本質は、感情や個人の物語ではなく「構造・関係・制度」の文学化であるところ。この部分が、少なくとも虚構モチーフレベルでは個人や恋愛や人間関係などに焦点があっているように思える物語性に対して、私の関心であるところの「社会システム/構造/主体/接続」などに関連して浮かびあがるところが個人的な好みとも合致するのだろうし、その核心4作はまさにその構造を示していたため、おそらく他著作でも同様の類似点が見つかるはずで、他もおいおい読んでいきたいと思う。
現時点で今回読んだ3冊だけでも著者の文学性の純度や角度は分かって、楽しかった。
モチーフや題材性を重視しがちな私の読書観では、かつて読んだ『袋小路の男』などが実はどのような主題や構造を描いているのかの読解が出来なかったために、小さな作品だと認識した危うさ、現実的にはモチーフや題材性の大商は構造や主題が描ければあまり関係がないことも知り、反省した。
題材性とかの広さはないが、別にそれだけが文学では勿論ないし、そのあたりを20歳前後の私は認識できなかったが、今思えば、日本文学的な狭さを継承しながらも関係性の文学を発端的に書き始めた著者の新しさや価値は目を見張るものがあるのかなと。
少し長くなるので②に続きます。
今回触れたように、会社員小説の要素として被りがあるように思える津村記久子を思い出しながら、構造と批評性のそれらとは別の労働や社会性、そうした価値観や世界観に至る作家性や人生、その唯一無二性などなど。芥川賞企画、一気に動き出した感が有ります。絲山秋子さん、お勧めです。







コメント